2024年12月
2024年10月に脳腫瘍の患者会“小児脳腫瘍の会”が実施したお泊り親睦会に、エ ーザイ社員6名が参加しました。また2024年2月には、創薬に関する知識をつけたいという同患者会からの要望を受ける形で、筑波研ラボツアーを実施し、患者会からは33名、エーザイ社員は19名が参加しました。


今回のこの2つの活動は、「小児AYAがんプロジェクト」と名付けられたhhc活動の一環で開催されたものです。エーザイ社員は2019年より“小児脳腫瘍の会”が実施するお泊り親睦会に参加しています。
当時てんかん関連プロジェクトに従事していた研究者の福島一幸は、かねてより神経領域とがん領域に強みのあるエーザイだからこそ、脳腫瘍患者様のアンメットニーズに応えていける素地があると考え、脳腫瘍に関する社外の意見交換会に参加しました。そこでお会いしたある脳腫瘍患者様に紹介いただく形で、患者団体のお泊り親睦会へ参加することになりました。
複数の患者様やご家族との対話を通じて、脳腫瘍そのものに加え、脳腫瘍に付随して生じるてんかんやその治療のために服用している抗けいれん薬の副作用で、その方らしい生活を送れていない実情を知りました。一般的に、てんかんの治療満足度や薬剤貢献度は高いと報告されており、このギャップに疑問を感じた福島は、教科書や論文では拾い切れていない患者様やご家族の憂慮があるのではと考え、てんかん患者様やそのご家族にお話を伺うことにしました。
コロナ禍で対面での対話が難しい中でも、リモート環境も活用しながら患者様との対話を地道に続けてきました。継続的な対話を通じて、患者様やご家族の本心が少しずつ垣間見られるようになり、脳腫瘍患者様、てんかん患者様に共通する憂慮への理解を深めることになります。それは、「副作用のない薬が欲しい(薬に日常生活を奪われたくない)」、「てんかんが治る薬が欲しい(薬の効き目を実感したい。効き目の実感できない薬を飲み続けたくない)」ということでした。
「患者様やご家族に必要とされる薬を作りたい」。福島は、従来の発想を転換します。従来の対症療法ではなく、てんかんの病態そのものに作用しててんかんを治癒するという創薬コンセプトを考え、プロジェクトを始動させました。また、福島の強い想いに共感した同僚の力を借りて、非臨床モデルにおいて長期にわたる投与試験とその評価を繰り返すことで、当初の創薬コンセプトの証明を行い、その後もプロジェクトを前進させています。
福島には、創薬に携わる研究者として譲れない“All for patients(全ては患者様のために)”という信念があります。彼は自分が関わる全てのプロジェクトを進める前に、必ず患者様とそのご家族に会いに行き、そこで聴き、感じた想いをプロジェクトに込めることを大切にしています。それは彼の2つの原体験に基づいています。
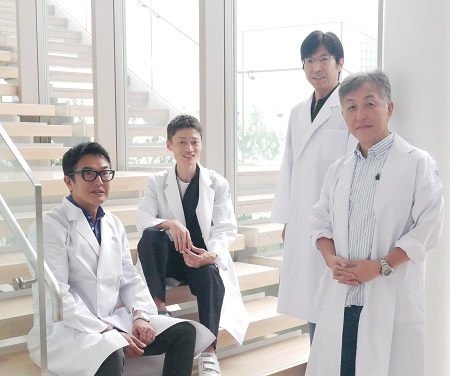
プロジェクトの仲間とともに
(左から二人目が福島)
一つは福島自身が、中高生の頃に原因不明の病に侵され死を覚悟したことです。原因が分からず点滴のみの入院生活を送り、「早く家に帰りたい。学校に行ってこれまで通りの学生生活を送りたい」と、ただただ願う辛い日々を経験しました。もう一つは、娘の心臓疾患です。我が子が心臓に疾患を抱えていることが分かった後、死に物狂いで疾患そのものや治療法、予後についての情報をかき集めたり、術後の精神的な負担が少ないよう傷が目立たない手術法やその手術に長けた医師を探し回ったりした経験があります。研究者となってからは、患者様がもし自分や自分の家族だったらと想像力を膨らませ、その“当事者”のために必死になることが、彼の創薬活動に一貫して根付いています。
福島は言います。「ある患者様から言われた“わたしたちを見捨てないで”という言葉が頭から離れることはありません。今回、患者様とご家族との対話(共同化)から生まれた創薬コンセプトを仲間の力も借りて証明することができましたが、“自分だったら”“自分の家族だったら”と想像を膨らませると、ここで喜んでいるわけにはいかないのです。こうしている間にも、患者様やご家族は苦しまれています。今後さらに社内外の協働の輪を広げていくことで、患者様が必要としている薬を一日でも早く届けられるよう努力を続けます。」

エーザイは、共同化を起点としたhhc活動を通じて感じ得た患者様の憂慮を、これからの創薬活動に活かし、今後も患者様のための医療の実現を目指してまいります。
