 |
 |
 |
コレラの本格的な流行は、第一次流行が文久2年(1862)にさかのぼり、その後も数年おきに流行が繰り返された。
ドイツ人Robert Kochが明治16年(1883)エジプトでコレラ菌(Vibrio cholerae)を提唱してから、細菌学的、免疫学的な研究も進歩した。
コレラは症状の急な激しい下痢と脱水症状を伴うため、手当が遅れると60から70%の高さの致死率とされた。その急な激しい症状は、一日に千里を走るとされた虎のイメージをもって受けとめられた。「虎烈刺」「虎列拉」「虎列刺」などの感じが当てられた。他に虎狼痢、古呂利、頃痢などといわれた。また、ころりと死ぬでコロリ(虎狼痢)ともいわれた。 |
 |
|
|
 |
|
 |
|
 |
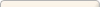 |
 |
「流行病(りゅうこうびょう)追討(ついとう)戯軍記(おどけぐんき)」 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
| |
|
|
 |
|
 |
|
 |
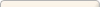 |
 |
「アジア国にてコレラ病伝染のやまひにて俗にコロリというなり」 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
|
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
 |

