 |
「セメンシイナ丸」
 |
 |
| むしって何? |

 |
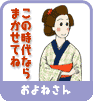 |
【「虫」の種類】
「虫」は2つあって、ひとつはいわゆる「寄生虫」。寄生した動物(宿主)から養分を横取りして生きる動物で、回虫・条虫・蟯虫などのことです。もうひとつは、身体の中にいると考えられていた「虫」のことです。赤ちゃんの体内にいる「虫」を「疳の虫」と呼び、夜泣き・乳吐き・ひきつけなどを引き起こすと信じられていました。
【虫退治】
昔の人は、この2種類の「むし」を区別していませんでしたが、とにかく病気の原因であると考え、「虫下しの薬」を用いてきました。
とにかく、お母さんにとってもこどもにとっても「疳の虫」はタイヘン!神社やお寺でも、虫封じの鈴を授けたり、こどもの「虫封じ」という行事を行うところもあるのよ。
ちなみに「疳の虫」の「疳」は、東洋医学の「五疳」のことで、「心疳」「肺疳」「脾疳」「腎疳」「肝疳」をいいます。この5つは病気のある症状を指すもので、病名ではなく、また時代や学派によっても解釈が違う場合があります。
寄生虫は今でこそ少なくなりましたが、江戸時代は人間の排泄物を肥料として用いていたため、排泄物とともに体外へ出た卵が、農作物を通じて次から次へと感染!寄生されると栄養失調になったり下痢を起こしたり、倦怠感がひどくなって日常生活に影響が出るんですって。まあ、生死に関わるほどの病気ではないものの、大変やっかいな病気でした。
「セメンシイナ」というのは、「シナ花」のつぼみを乾したもので、ここからサントニンという薬品を作って駆虫薬にしました。最初はロシアから輸入してたんだけど、昭和15年に国産化に成功。年配の方は、学校で月に1回、にが〜い虫下しを飲まされた経験をお持ちだと思います。あまり飲みにくいので、チョコレート風の味をつけた「くすり菓子」も用いられました。
【虫・・・のつく言葉】
「虫が好かない」「虫がいい」「虫の居所が悪い」「虫酸が走る」「虫が知らせる」「虫がつく」「泣き虫」「弱虫」「ふさぎの虫」「本の虫」
【庚申待ち】
中国の神仙思想の影響を受け、庚申の夜に一晩中起きていないと、身体内の「三尸(さんし)」という虫がその人の悪行を天に上って報告するという“庚申信仰”も信じられていました。
【虫送り】
作物の害虫を取り除くため、村人が大勢で松明をともし、鐘や太鼓を鳴らして村はずれまで稲虫の人形を送り出す行事。 |
|

