

手術の起源は古く、古代エジプトや古代ローマ帝国でも行われていた。

古代においては外科手術の麻酔として、マンドレークを、また9世紀のアラビアや中世イタリアでは、アヘン・マンドレーク・ヒヨスなどの薬剤を用いたとされる。アルコール飲用も古くから使用されたが、ひどい痛みには効果がなかった。

16世紀に戦争で銃火器が使用されるようになり、その傷の手当てには熱した油や焼き鏝(やきごて)が用いられたが苦痛がはなはだしかった。その後フランスの外科医・パレが塗り薬のみで治療する方法や、血管結索法を考案・実施した。

日本で、1804年に華岡青洲が乳がん手術時に、全身麻酔剤を用いた手術を成功させていたが、普及はしなかった。

近代に麻酔薬として登場したのは、笑気(亜酸化窒素)、エーテル、クロロホルムである。アメリカの医師・モートンは1846年、エーテル麻酔で腫瘍(しゅよう)の除去手術を公開を行い、成功した。クロロホルムは1831年に発見され、 1847年産科の手術時に麻酔として用いられた。


医師の手指や病室、手術台など、診察する環境において清潔という観念が着目されるのは18世紀になってからであった。

オーストリアでは、ハンガリー人医師・ゼンメルワイスが1847年に手指を水と消毒液で洗うことを提唱した。この方法を実施したところ、彼の勤務する病棟の死亡率が大幅に減少したが、当時の医学界にこれを支持する人は少なく、消毒法が普及するようになったのは、19世紀後半であった。
|
 |
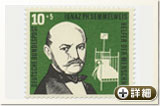
切手「ゼンメルワイス」

切手「リスター100年」
|
|

