

古代から中世にかけてのヨーロッパは、病気は天体や気候の影響で体液が異変を起こして発病するものと考えられていた。

16世紀初にスイスのパラケルススが自分の体験や観察、実験に基づいた臨床医学を推し進め、その後、オランダのヴェサリウスが近代解剖学を確立、イギリスのハーヴェイが血液循環説を提唱した。また18世紀後半には、イギリスの外科医・ジョン・ハンターが数多くの解剖を実施し、人体の仕組みについての研究は次第に進んでいった。


病人に触れたり、病気が流行している地域を通ると発病することがあることは、経験により古くから知られていた。

そのため、中世ヨーロッパでは検疫が行われ、16世紀イタリアのフラカストロは感染の経路が数種類あることに既に気づいていた。 17世紀イギリスの医師・シデナムは病気の経過に注目し、病気を3種類に分けた。

1796年イギリスの医師・ジェンナーは天然痘の予防接種を提唱した。

フランスの化学者・微生物学者のパストゥールは、1861年に空気中の微生物が腐敗を引き起こすことを発見し、 1881年以降に炭疽病ワクチンと狂犬病ワクチンを創製し、ジェンナーのワクチン療法の理論が有効であることを証明した。

1882年にコッホは結核菌の純粋培養に成功し、病気を発症させる細菌の確定するための条件を「コッホの原理」として定めた。

微生物の分離と同定の技術や理化学機器の開発が進んだため、19世紀から20世紀初頭にかけて、各国の研究者が病原菌を発見することができた。
|
 |

切手「ジェンナー」
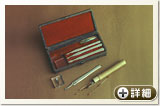
痘苗接種用具

ロバート・コッホ来日記念写真
|

