

メソポタミアの粘土板や古代エジプトのエーベルス・パピルスにも記述があるように、ケシが古くから鎮痛薬として用いられていた。

1世紀頃には、ローマ時代のディオスコリデスが、ケシからアヘンを採取する方法を記述した。アヘンは、少量では鎮痛・誘眠などの作用があるが、大量に服用すると昏睡状態に陥って死亡することも既に知られていた。

9世紀にはアラビアの医師らが、アヘン、マンドレーク、ヒヨスの液をしみこませた海綿を麻酔薬としたといわれている。

1806年、このアヘンから有効成分・モルヒネを純粋な結晶として単離したのは、ドイツの薬剤師・ゼルチュルナーである。彼は何度か実験を重ね、有効成分の研究を進めた。


ヨーロッパではギリシア時代から痛風には、ヤナギの一種(Salix alba セイヨウシロヤナギ)の樹皮の煎じ汁を罨法剤(あんぽうざい※)として用いてきた。

リウマチ、神経痛、歯痛の痛み止めとしても使用してきた。

1763年にイギリスのストーンがこのヤナギの抽出物を解熱剤に用い、1830年にルルーがサリシンを抽出、1838年にはピリアがサリシンを分解してサリチル酸を得た。

同じ頃、ドイツのレーウィッヒがSpitaea ulmaria(セイヨウナツユキソウ)の花の揮発油から新しい酸を得て、スピール酸と呼んだ。1853年にコルベによりサリチル酸とスピール酸が同一物質であると確認された。

当初、サリチル酸は酒の防腐剤として用いられ、やがて鎮痛・解熱剤として利用されるようになった。

1860年にゲルハルトがアセチルサリチル酸を合成し、ホフマンは1897年にそれを純粋な形で合成することに成功した。 1899年にこれをアスピリンと命名し、販売するに至った。
| ※罨法剤= |
炎症や充血を取り除くため、患部を温めたり冷やしたりするのに用いる薬 |
|
 |

看板「医薬用阿片販売所」

セイヨウナツユキソウ
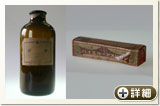
サリチル酸・アスピリン(薬品2点)
|

