

フレミングは1928年、ブドウ球菌の実験中、寒天培養地に混入した青カビを培養した培養液の中に細菌の発育を阻止し、溶かす作用があることに気づいた。

この培養液をろ過して得た物質を、彼は青カビの学名にちなんで、ペニシリンと命名した。 1941年には、オーストラリア出身の病理学者・フローリーとドイツ出身の生化学者・チェーンがイギリスの研究者たちとともに大量生産の方法を開発し、1944年にはアメリカとイギリスで大規模生産が行われるようになった。

日本では国際ペニシリンの開発が進められた。

陸軍軍医学校では軍医少佐・稲垣克彦を中心に、当時の医学・薬学・農学・理学の各分野の研究者が集められ、 1944年(昭和19)、ペニシリン委員会が結成され、約8ヶ月で精製に至り、翌年には“碧素(へきそ)”と名付けられたペニシリンが完成した。戦後は連合軍が進駐し、ペニシリン生産を推し進めた。

ロシア出身のワクスマンはアメリカでシャッツと共に研究を行い、1944年ストレプトマイシンを発見した。

この物質は毒性が低く、ペニシリンが効かない結核菌にも効果があることが判明した。
|
 |

ペニシリン・青カビ模型

ペニシリン(集合写真)

ポスター「結核ノ知識ト予防」
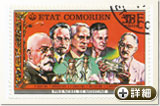
切手「コッホ、モーガン、フレミング、ミュラー、ワクスマン」
|

