
|
 |
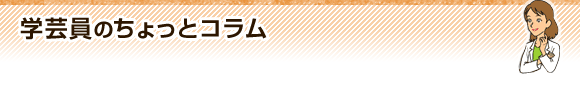 |
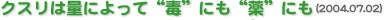
 |

|
もうすぐ楽しい夏休み、博物館では“夏休み親子教室”を開催します。昨年に引き続いて今年も、「さおばかり(桿秤)」の歴史を学ぶと同時に、参加者一人ひとりにさおばかりを作っていただきます。
さおばかりは、数多くある重さばかりの種類の中でも、簡易式で携帯にも便利につくられている秤です。意外と簡単に作れますので、工作を楽しみながら秤の仕組みを学んでいただけることでしょう。
そもそもはかることは「科学の基本」ともいわれていますが、日常生活の中で、私たちは無意識に食べ物や体重など、モノの重さを比べたりはかったりしています。
私達がこの世に命を授かって最初に触れる秤は、生まれたときにはかった体重計でした。秤には長い歴史があります。目的や用途に応じて多くの種類が誕生しました。また、古代エジプトでは、死後に冥界の王オシリスの裁判で、天秤は死者の罪業をはかる神の道具として使われました。羽毛は地上で最も軽いものとされ、人間の心はそれよりもさらに軽くなければならず、罪深い人ほど心臓が重くなるとされました。羽毛より軽い心臓を持つ魂だけが天に導かれたとされています。
実用面では、古くから商取引において無くてはならない秤ですが、薬との関わりも深く、昔から薬や医療に携わる人々は、わずかな薬物の増減を大切にしてきました。そのため少量のモノを例える表現として、『薬ほども無い』といいますし、使用量がとても大切!という意味をこめて、『匙加減』というように、患者の体質や具合に応じて量の加減を見ることができる医師こそが名医とも謳われました。病気や怪我を治療したり予防する薬は、『量によって“毒”にも“薬”にもなる』ともいわれ、微量で大きな影響を及ぼしますので、細心の注意が必要です。
くすり博物館では歴史的な秤を多数所蔵しています。「長さ」「容積」「重さ」をはかるための道具、尺(しゃく)や枡(ます)そして秤類など、度量衡関係の資料は約1,000点余りがあります。はかるモノの特徴や用途、時代やお国柄によって、実にさまざまな形の秤と分銅、錘(おもり)がありますよ。
● 度量衡 >>
|
|
|

