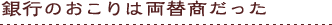
江戸時代の商人の中から、貨幣交換を生業とする両替商が登場しました。江戸時代の貨幣には金貨、銀貨、銭貨の三種類があり、それぞれが独立していて市場では銭貨を使うのが一般的でした。
基準レートとしては、金貨1両=銀貨50匁(元禄以降は60匁)=銭貨4貫文(4000枚)と換算率が定められていました。しかし、実際には民間の相場によって変動し、幕府の財政窮乏から金の含有率が下がると、交換率が悪くなりました。こうした背景から、両替という商売が成立し貨幣市場を形成するようになりました。これが銀行のおこりです。両替用の天秤と分銅は両替商を象徴する道具でした。そのため地図上で銀行を示すマークとして分銅の形が使われました。
銀貨は重さによって価値が異なる秤量貨幣だったため、流通のつど重さを調べてから取引しました。そこで、銀貨をはかる携帯用桿秤を「銀秤」と呼びました。また、江戸幕府直轄で銀貨を鋳造していた場所の一つが東京都中央区の銀座、金貨を鋳造していた座の一つが現在の日本銀行の場所にあり、金座と呼ばれていました。
|

