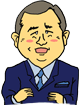 |
本格的な秋の到来を迎えました。さて、秋といえば「読書の秋」、それは知的好奇心を満たしたくなる季節といってもいいのではないでしょうか。そこで、当館ではホームページでもご紹介のとおり、この秋より日本の「くすりと医療の歴史講座」を新たに開設いたしました。当館は、薬学や医学に関する歴史的資料を65,000点、書籍を62,000点収蔵していますが、この講座でこれらの資料や書籍を通してより多くの皆さんにくすりと医療の歴史を楽しく学んでいただき、大いに知的好奇心を満たしていただきたいと思っています。
ひとくちに、くすりと医療の歴史といっても長く、簡単に説明はできませんが、近代に至るまでの大きな節目として考えられるのは、「医療のあけぼの」の飛鳥・奈良時代、「くすりと医療が大衆化」した江戸時代、「くすりも維新」の明治時代ではないでしょうか。中でも江戸時代は、戦乱のない平和な時代が長く続いたこともあり、街道が整備され商業が発展しました。くすりがお店で販売される一方、街頭でもくすりが売られ、庶民でも手軽にくすりを手に入れることができるようになりました。また、あの有名な富山の配置売薬も始まり、地方や山間部にもくすりが届けられるようになり、多くの人がくすりの恩恵を享受できるようになりました。また、江戸中期になると養生の概念が発達し、人々は健康に関心を払うようになり、病気にならないための知識を身につけました。養生に関する書物では貝原益軒の「養生訓」が有名ですが、他にも養生に関する書物が多く出版されました。
一方、それまで中国医学一辺倒だった医学の面でも新しい動きが起こります。それは人体解剖です。それまで、わが国では人の体を切り開いて臓器を観察することはご法度でしたが、1754年に京都所司代が初めて人体解剖を許可しました。その5年後、その解剖に立ち会った山脇東洋がその様子を「蔵志」として出版しました。これが、わが国で最初の解剖図です。そして、1774年に杉田玄白がオランダ語の解剖書「ターヘル・アナトミア」を翻訳した「解体新書」を出版し、西洋医学に対する関心が一気に高まります。これは、それまで人体の構造を「五臓六腑説」で考えていた中国医学の誤りを正すことになります。
こういった事柄だけでも、どうして富山で配置売薬が有名になったのか、「養生訓」(全8巻)にはどんなことが書いてあるのか、「解体新書」はどのような経緯で出版されたのか、中国医学の「五臓六腑説」とはどのような考え方なのか等々を知ることによって、さらなる疑問が湧いてくるはずです。そして、その疑問が解決されると、また新たな興味が湧いてくるに違いありません。
このように次から次へと知的好奇心が生まれ、その階段を駆け上がっていけたら素晴らしいと思います。より多くの方のご参加が待ち遠しいこのごろです。 |
|

