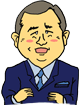 |
寒い毎日が続いています。このシーズン、インフルエンザの流行も気になるところです。
インフルエンザといえば、感染症の代名詞のようにいわれますが、古くは感染症のことを「はやり病」といい、江戸時代からあったようです。奥医師(将軍やその家族を診療した)だった伊東玄朴がドイツの内科書を翻訳した書物の中でインフルエンザに「印弗魯英撤」という漢字をあてていますが、これがわが国でインフルエンザの病名が活字になった最初といわれています。それにしてもこの漢字、何とも味わい深いです。
江戸時代には他にも沢山の感染症があり、人々を苦しめました。疱瘡(天然痘)、麻疹、コレラ、梅毒などが代表的なものでした。当時は、これらの感染症に対して決定的な治療法がなく、不治の病で多くの人々が命を落としたといわれています。中でも梅毒は難病中の難病といわれ、江戸や大阪では病人の八割は梅毒だったといわれています。羽生和子氏の著書「江戸時代、漢方薬の歴史」によれば、江戸時代に梅毒の治療薬として珍重されたのが「山帰来」で、当時中国から輸入された薬の中ではダントツの多さだったようです。このことからもいかに多くの梅毒患者が存在したかがわかります。ご存知のように梅毒は、コロンブスが新大陸からヨーロッパに持ち帰ったとする説が有力ですが、モーパッサン(フランスの作家)、ハイネ(ドイツの詩人)、ニーチェ(ドイツの哲学者)、シューベルト(オーストリアの作曲家)、ゴーギャン(フランスの画家)などヨーロッパの著名な芸術家も梅毒で命を落としたといわれています。
もし当時、今日のような決定的な治療薬があれば、彼らはもっと多くの傑作を残してくれたに違いありません。特に、シューベルトの大作「未完成交響曲」も「未完」で終わることはなかったのではないでしょうか。
平成23年度の当館の企画展では、上記のような日本人を苦しめてきた感染症や病気に対して、当時の人々がそれらの病気をどのようにとらえ、対処しようとしたのかにスポットを当てます。題して「病まざるものなし−日本人を苦しめた感染症・病気 そして医家−」。4月下旬に開催予定です。ご期待ください。 |
|

