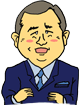 |
先日、全国博物館大会が「歴史文化と博物館―1300年の時空を探求―」をテーマに奈良で開催されました。奈良を訪れるのは小学校の修学旅行以来のはるか昔。私にとっては、まさに50年の時空を超えての訪問でした。当時いろんなところを見て回ったはずですが、記憶にあるのは東大寺の大仏様ぐらいでしょうか。猿沢の池にも行ったはずですが、池の畔に佇んで美しい紅葉を眺めても当時の記憶が戻ることはありませんでした。

復元された遣唐使船 |
ご存知のように、今年は平安遷都1300年ということで多くの人が奈良を訪れています。特に大極殿は当時のままに復元され、遷都1300年祭のシンボル的存在で連日の賑わいを見せています。1300年祭の期間中は、長さ30メートル、幅7〜9メートルで150名ほどが乗り込めた遣唐使船も復元され、展示されました(写真ご参照)。
最初の遣唐使が派遣されたのが紀元630年、最後の遣唐使の派遣となったのが紀元838年。この間約200年にわたり、遣唐使船に乗った遣唐使によって当時の唐(中国)を中心とする東アジアの情報や先進的な唐の文化が日本にもたらされました。医学、薬学も唐からもたらされたと言われており、正倉院には、当時の生薬がそのまま保管されています。現存するわが国最古の生薬ということになりますが、今年の正倉院展では、そのうち「龍歯」(ナウマン象の歯の化石)、「大黄」、「冶葛」(やかつ)の3種類の生薬が一般公開されました。「大黄」と「治葛」はいずれも植物ですが、「大黄」は、健胃・消炎に効果があるとされ、「冶葛」は皮膚疾患の外用薬の他には、鳥獣捕獲としても用いられていましたが、毒性が極めて強いため現在ではあまり用いられていないようです。しかし、驚くべきは、今なお「大黄」は有効成分を留め、「冶葛」も毒性を留めていることです。
遣唐使船による唐への渡航は、極めて危険をともなうものでした。はじめのころは2隻の船団でしたが、8世紀以降は4隻の船団で渡るのが普通になりました。それは、多くの船が沈没したり、遭難するためどれか一隻でも唐に渡るためだったようです。正に命がけの留学であり、遣唐使に任命されても拒否する人もいたようです。しかし、多くの遣唐使は命を懸けて唐にわたり、わが国に医学や薬学の知識を伝えてくれたわけです。1300年の時空を超えて、「大黄」や「冶葛」がいまなおその効能を留めているのは、遣唐使の命を懸けた熱い思いの証かもしれません。 |
|

