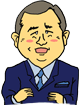 |
博物館に赴任して1年が経過しました。いつまでも新米館長でいるわけにもいかず、この間、岐阜県の博物館協会、東海地区の産業観光推進懇談会、企業博物館の集まりである産業文化博物館コンソーシアムなどにも顔を出し、各館の取り組みに感心させられたり、課題に同感したり、いろいろと勉強をさせていただいています。そして、思うようになったこと、それは我が「くすり博物館」の存在意義。何のために「くすり博物館」は存在するのか。もう一度、見直してみようと。
博物館等ミュージアムの評価基準のひとつとして、来館者数があります。前年比何%増えたとか、減ったとか、そんなことがよく話題になります。来館者数は少ないより多いことに越したことはありませんが、来館者数が増えたからといって手放しで喜んでいいものかどうか。来館者数はあくまでも結果であって、問題は、何人のひとに本当に喜んでいただけたのか、ご満足いただけたのかが大切ではないか。そこに存在意義があるのではと。やはり、博物館は中身で勝負。いろんなイベントをやって人集めに奔走することばっかりに目がいくと、博物館本来の目的を見失うことになりはしないか。
来ていただいたお客様に本当に、「くすり博物館」に来てよかった、また来てみたいという気持ち、すなわち感動を与えられる博物館にしたいのです。どうしたら、感動していただくことができるのか。感動につながるキーワード、それは新しい発見であったり、驚きであったり、それまで、その人が思ったり、経験したことがないことを体験させてあげることではないか。展示資料の単なる陳列ではなく、その資料がもつ意味合いや、価値をうまく引きだし、誰にでもわかるように説明を加える。そのためには、展示資料をよく調査、研究し、その資料のもつストーリーや、新しい知見をどんどん提供していくことが大切ではないか。また、より感動を高めるためには、五感で感じる心地よさを提供することも必要ではないか。照明はこれでよいのか、導線は、解説パネルの位置は、色合いは等々、いろいろなことが頭をよぎります。
感動は、ご来館いただいた方に、また来てみたい、行ってみたいという気持ちにさせ、回りの友人や知人にも勧めてくれることでしょう。そして、その友人や知人もその感動を、次の人に伝えてくれると思います。そして、その結果としてより多くの方々が「くすり博物館」のファンになってくれたら、これに勝る喜びはありません。ひとりでも多くの方に感動を与えられるような「くすり博物館」を目指していきます。館長就任2年目の試練かも・・・・・。 |
|

