
|
 |
 |
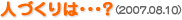
 |
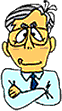
|
昨年の教育基本法改正に続き、6月20日に教育改革関連三法が参院本会議で可決された。昨今、わが国の児童・生徒の学力低下が云々されているが、文部科学省が推進してきた「ゆとりの教育」の副作用か。今、教育の現場で何が起きているのか知る機会もないし、その課題を論ずる気もない。ただ、熾烈な競合が展開される世界で、わが国が遅れをとらないことを祈るばかりである。
江戸時代の教育機関は、幕府直轄の「昌平黌」、各藩の「藩校」、庶民のための「寺小屋」等々があるが、明治国家の礎を築いた人づくりに「私塾」が果たした役割は大きいと言われている。江戸時代の私塾といえば、吉田松陰の「松下村塾」、中江藤樹の「藤樹書院」、シーボルトの「鳴滝塾」等々が知られているが、緒方洪庵の「適塾」もその一つである。
緒方洪庵は備中の産、中天游に蘭学を学び、坪井信道、宇田川玄真に師事して医学を学んだ後、長崎でカピタン・ニーマンの教えを受けた。貧しかった洪庵は蘭書の翻訳アルバイトをしながら勉学を続けたという。
天保九年(1838)、洪庵は大阪瓦町で医を業としながら、適々斎塾(適塾)をひらいた。洪庵は「大阪除痘館」を設けて種痘の普及に努め、コレラの流行に「虎狼痢(ころり)治準」を書いて治療法を指示するなど医師として大きな功績を残したが、同時に、「適塾」における優れた教育者でもあった。名声の高まりと共に塾生も増え、入門帳には600名をこす名が残されており、常時50名前後が合宿していた。彼の門からは、後に慶応義塾を興す福沢諭吉、安政の大獄で処刑された志士・橋本左内、幕軍として徹底抗戦した大鳥圭介、逆に官軍側の大村益次郎、日本赤十字社の創始者・佐野常民、内務省の初代衛生局長などを務めた長与専斎等々多くの逸材を輩出した。「適塾」における教育はつねに緊張感に満ち、書生の意気込み、蛮カラを伴う勉強の激しさ楽しさが語られている。オランダ語の基礎を約1年間で叩き込んだ後、毎月6回開催される会読に参加を許される。上級生を会頭とする10〜15名のグループで順番に原文を解読し、全員で容赦ない質問と議論を展開する。会頭は必ず勝敗を下し、結果を個人の成績として残した。合宿所では成績優秀の者から順次窓際の明るい場所を選択する権利が与えられた。一部しかない医学書などの原書を筆写し、一組だけの蘭和辞書「ズーフ・ハルマ」の写本を活用し競って勉学に勤しんだ。
最近では、運動会の徒競走においてすら順位を決めない学校があると聞く。実社会では、嫌でも競合の中に曝されることが避けられるはずもないのに。
 |
|
|

