
|
 |
 |
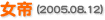
 |
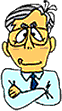
|
最近、わが国で女性の天皇を許容すべきかどうかの議論が再燃している。単純に発想すれば、男女平等の世の中であり、エリザベス2世が君臨するイギリスやオランダでは容認されていることから、当然認められてしかるべきと考えてもおかしくない。しかし、そう単純な問題ではないらしい。皇位継承や皇族の範囲は「皇室典範」という法で定められていることはよく知られているが、明治22年(1889)の旧典範を制定したときにもすでに女帝是非論があったという。ましてや民主憲法といわれる昭和憲法において議論にならないはずがない。にもかかわらず、昭和22年(1947)に公布された新典範においても女性に皇位継承の資格は認められなかった。
この論争に参戦する気は全くないが、我が国の歴史においても、過去8人10代(内2人は重祚:一度退位した天皇が再度皇位につくこと)の女帝の時代があったという事実に興味を引かれた。
歴史上、最初の女帝は推古天皇(33代、在位:592〜628、以下同様)である。以後、皇極(642〜45)・斉明(重祚:655〜61)、持統(690〜97)、元明(707〜15)、元正(715〜24)、孝謙(749〜58)・称徳(重祚:764〜70)、明正(1629〜43)、後桜町(1762〜70)と続く。不思議なことに、飛鳥・奈良時代に集中して誕生しており、長い空白期間の後、江戸期に再び現れた。
過去の女帝誕生はあくまでも暫定処置であったというのが、女帝を容認しない一つの根拠となっている。しかし、推古天皇の在位は75歳で没するまでの37年間におよんでおり、とても暫定政権とは思えない。推古天皇は『古事記』では豊御食炊屋比売(とよみけかしきやひめ)と記されている。第29代欽明天皇の皇女として生まれた推古天皇が即位するまでの経緯はややこしいので省略するが、周知のように、甥の聖徳太子を摂政に立て、叔父の蘇我馬子(大臣)とのトロイカ方式で安定政権を維持することにより、国家仏教としての発展、外交面で遣隋使の派遣、十七条憲法・冠位十二階を定めるなど、当時として大きな業績を残した。また、推古天皇は611年、百官を率いて大和莵田野に薬狩りをしたことが『日本書紀』に記されている。わが国最初の薬草採取の記録であり、以後、5月5日を「くすり日」と称した。姿色端麗・進止軌制と『日本書紀』にあるが、くすり博物館の壁画に描かれた姿もなかなかの美人である。
今後、皇位継承論議がどのように展開するか予測は難しいが、現代の世に推古天皇再来もまた興味ある。
|
|
|
|

