
|
 |
 |
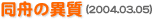
 |
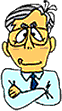
|
人間関係の難しさは誰しも経験があろう。日頃、親しい人でも、時には、その言動を苦々しく感じることもある。ましてや、性格や考え方が異なり、できれば避けたい相手であるが、仕事の遂行上やむなく付き合わざるを得ないケースは、そのこと自体がストレスとなることも少なくない。
安永三年(1774年)八月、『解体新書』※本文四巻、附図一巻が刊行された。『解体新書』といえば、誰しも、杉田玄白と前野良沢を思い浮かべるが、著者として、翻訳作業における中心人物である良沢の名前は記載されていない。『解体新書』誕生までの経緯は良く知られており、多くを語る必要はないが、本書の刊行が、わが国の医学界に大きな革新をもたらせたことはまぎれもない。
千住骨ヶ原(現小塚原)の刑場で、罪人の腑分け(解剖)を見ることができるという情報を得た玄白は、良沢などを誘って赴いた。奇しくも玄白、良沢両人の懐には、オランダの解剖書『ターヘル・アナトミア』があることをお互いに知り、「これ誠に奇遇なり」と喜んだ。蘭語は殆ど理解できなかったが、腑分けの現場で蘭書の図と照合すると、寸分違わないことを知り両人とも深い感銘をおぼえた。帰路、玄白・良沢に中川淳庵の三人は、何とか翻訳したいと志を立てるが、蘭語については、一時、青木昆陽に師事し、長崎留学経験のある良沢は多少心得があるものの、玄白には殆ど未知の世界であった。『蘭学事始』に当時の玄白の心境が「誠に艫舵(ろかじ)なき船の大海に乗り出せし如く、茫洋として寄るべきかたなく、ただあきれにあきれて居たるまでなり」と記述されている。最初は、「眉とは目の上にはえる毛なり」というたった一句の翻訳に丸一日を費やしたという。時に、良沢49歳、玄白39歳であった。苦労の末、丸4年掛けて翻訳を完成するが、所々に誤りがあり、「此の語解せず」とかぶとを脱いだ個所も全篇で4つあるという。
『解体新書』の著者に、翻訳作業でリーダー的役割を果たした良沢の名前がないことに関し諸説がある。主には、翻訳が不完全なまま公開することに良沢が反対し、著者としての記載を拒否したという説、『解体新書』を刊行することにより、幕府からお咎めを受けることを懸念し、良沢にまで累が及ぶことを畏れた玄白が単独著者としたという説、良沢としては、蘭語の研究が第一関心事であり、功名心からではないことを大宰府天満宮に誓った説などである。両者の性格・考え方の違いから推測すると、どの説もあり得る話である。孤高の人・良沢は学究肌の完璧主義、世話役・まとめ役を務め、細かいことに拘らない鷹揚な人・玄白は合理的な現実主義者であった。
玄白は良沢に対して畏敬の念をもちながら、時として噛み合わない一面を感じていた節がある。しかし、学究的には良沢、企画・事業推進などマネジメントでは玄白の両人がいて、はじめて大事業『解体新書』が完成した。性格的なギャップがあっても、目的を共有すれば大きな仕事が成し遂げられる好例である。むしろ、大きなプロジェクトには、異質な人間の協働が重要かもしれない。
※解体新書
※収蔵品デジタルアーカイブ 解体新書
 |
|
|

