
|
 |
 |

 |
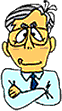
|
昨今、医療技術が高度化する一方で、医療過誤・医療事故の報道が後を断たない。その多くは単純ミスによるものと思われるが、未熟な技術の医師三人が、難度の高い腹腔鏡手術で前立腺ガン摘出に挑み、患者が亡くなったニュースには、やり切れない思いを払拭できなかった。
NHKの木曜日夜8時から「お江戸でござる」というコメディー番組がある。江戸時代の生活・文化についての杉浦日向子先生の解説がなかなか面白い。先般、シーボルトと土生玄碩(はぶ・げんせき)の話が番組の一部に登場した。
土生玄碩は江戸後期の眼科医で、宝暦12年(1762)、吉田(広島県)に生まれた。大阪、京都で医術を学び、浅野家の教姫(のりひめ)の目を治療したことを契機に、徳川幕府の御殿医に登用された。玄碩は江戸・長崎屋に逗留中の長崎・出島の蘭館医・シーボルトを訪ね、瞳孔を散大させる薬を所望したところ、最初は快く分与してくれた。しかし、もらった薬がきれたので再度分与を願うが、シーボルトに断わられた。窮余の策で、着ていた葵の紋服を与え頼み込んだところ、シーボルトは日本にもあることを告げた。シーボルトが持参していたのはベラドンナ(和名も同、美しい淑女の意)であり、シーボルトが勘違いして教えた日本の植物はハシリドコロであった。ヨーロッパ原産のベラドンナと日本のハシリドコロは、共にナス科の有毒植物で、ヒヨスチアミン(ラセミ体はアトロピン)やスコポラミンなどのアルカロイドを含み、瞳孔を散大させる作用があるので、白内障の手術などに威力を発揮した。
ところで、玄碩がシーボルトに与えた葵の紋服は、もとより将軍家拝領である。後に、玄碩は、文政11年(1828)のシーボルト事件でこの件の責を問われ、晩年の大半を刑に服することになる。すでに、幕府御殿医という地位・名声・富を得ていた玄碩が、敢えて国禁を犯してまで薬を入手しようとしたのは何故であろうか。常に新しい手術法を考案するために、あらゆることを貪欲に学ぼうという意欲に溢れる玄碩にとって、手術を容易にする散瞳剤を見逃すことができなかったのであろう。ひとえに、万人を救うことを最優先したと考えたい。
確かに、新しい試みにはリスクが伴う。しかし、華岡青洲の全身麻酔剤「通仙散」完成の陰には、母於継や妻加恵など身内の献身的な働きがあった。土生玄碩はわが身の危険を顧みなかった。現代でも、立派な医師がたくさん存在することに疑いの余地はないが、患者を第一義に考え、自己犠牲をも厭わないという気概が伝わる報道は多くない。
※ベラドンナ
※ハシリドコロ
 |
|
|

