
|
 |
 |
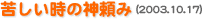
 |
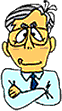
|
現代の日本人は比較的宗教に対して淡白だと言われているが、それでも生活のベースに少なからず宗教が絡んでいることを実感する。日頃、信仰心が極めてうすい筆者ですら、「ここで松井秀喜に一本打たせてくれ」と思わず手を合わせ神に祈ることも間々ある。勝手なものだと、神様も苦笑しているに違いない。
昔から神頼みの一つの典型として定着しているのは、絵馬の奉納である。毎年時期がくると、全国の天神さんの境内が「合格祈願」の絵馬で埋め尽くされる光景は、一つの風物詩とすら感じる。「所詮、実力・努力だよ」と言ったら身も蓋もない。切ない神頼みは微笑ましくも本人にとっては深刻である。
絵馬のルーツは、神の乗り物として神聖視されていた馬を献上したことに始まる。本物の馬を献上できないものが木製や土の馬形を、更に、馬形もつくり得ないものが馬を絵に描いて献上したのが絵馬の起りと言われている。発祥時期ははっきりしないが、伊場遺跡で奈良時代の絵馬が発見されている。平安時代末期には、神社だけでなく寺院にも広く奉納されるようになり、室町時代末期には、絵馬の画題も馬だけでなくいろいろなものがあらわれた。
健康祈願は今も昔も変わらない。特に、医療が不十分な時代には、病気の平癒を願う絵馬が少なくなかった。当博物館の展示品に健康に関わる絵馬※約30枚がある。“乳しぼり”はズバリであり、亀(長寿)、石榴(ざくろ:子宝、安産)などは比較的分かりやすいが、一見して、何を祈願したものか分からない絵馬も少なくない。「め」という字が二つ向かい合っている“向かい目”、目の型を八つ描き“病眼(やむめ)”は眼病治癒の祈願と想像できるが、松を逆さに描いて“逆さまつげ”の治癒とは傑作である。鶏は夜鳴かないところから小児の夜泣き封じに、牛は瘡(かさ:皮膚病)を草になぞらえ、食わせて平癒を願う。鎌を二本交叉させた“違い鎌”も同様に草を刈るところからきている。鳩は豆を拾って食べるところから手足の肉刺(まめ)に、蛸は吸盤で腫物や疣(いぼ)を吸い出す。鰯の銀鱗から蕁麻疹、強い臭いから性病を連想し描かれた。動物(鹿など)や魚(鰻など)がペアで並んでいるのは殆ど夫婦和合を願うものである。手を描いた絵馬は、中風、リウマチなど腕の病の治癒を願った。“三方上大根”が色白祈願とは思わずニヤリ。(岩井宏美著『絵馬』より)
同じ絵柄でも、土地柄や神社により祈願の目的が異なることもある。
本コラムもネタ探しに苦心。苦しい時の神頼みを「絵馬」に求めた。
※絵馬
 |
|
|

