
|
 |
 |
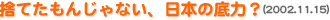
 |
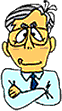 |
世界規模での新薬開発競争にドップリ浸かった修羅場から、「くすりの歴史と文化」を伝える静寂の博物館に180度転換したのは本年7月である。博物館研修会に参加した折、博物館館長の仕事について尋ねてみた。元大学教授の学者館長さん、全国を股にかけて講演活動され、動く広告塔と言われている館長さん、小学生の誘導から展示品の移動まで何でもやられる館長さん等々、千差万別である。
毎日、3人の美人で賢明な学芸員に叱責され右往左往している館長が一人位いても不思議ではない。
最近、暗いニュースが続く中で、ノーベル賞ダブル受賞は、我々日本人にとって一服の清涼剤であった。小柴昌俊東大名誉教授(物理学賞)の満を持しての受賞に比べ、田中耕一氏(化学賞)は下馬評にも上らず、正に寝耳に水の朗報との報道である。学者とサラリーマン、76歳と43歳、宇宙と蛋白質など色々な側面で両氏が全く対照的であることも興味深い。
特に、田中氏の受賞は世のサラリーマン研究員に大きな光明を与えると同時に、氏の素朴な言動に、ノーベル賞とは全く無縁な我々にもより身近なものと錯覚させる効果もあった。田中氏の研究を高く評価した推薦者およびスウェーデン王立科学アカデミー選考委員会の決定に盛大なエールを送りたい。
ノーベル賞が1901年に制定されてからすでに一世紀が経った。100年の歴史をほぼ2分した1945年(第二次世界大戦終戦)までの自然科学3分野の受賞者数は、ドイツが36名で首位、次いでイギリス25、アメリカ18の順であった。日本人の受賞はない。1946−2000年間では、アメリカが180名でダントツのトップであり、イギリスの41、ドイツの27を大きく引き離している。因みにこの間の日本人受賞者は6名を数え8位にランクされる(以上東北大資料引用)。技術立国日本も未だしの感があるが、科学技術会議の答申によれば、21世紀「50年間にノーベル賞受賞30人程度」という数値が示されているという。50年後にも生存されている方にご確認願おう。がんばれニッポン!
|
|
|

