 |
 |
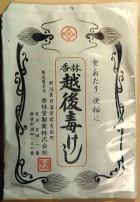
越後毒消し

越後毒消しの原料「菊明石」

越後の毒消し売りの行商人
本来は菅の爪折笠をかぶる。
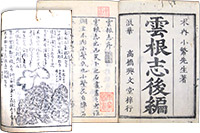
雲根志 後編巻之1-4
木内石亭著 大坂 高橋平助 1773(安永2) 40633
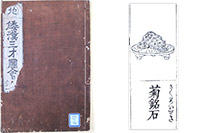
和漢三才図会 目録・巻第1-105
寺島良安編 大野木市兵衛 1713(正徳3) 38747
|
毒消しとは
中国医学由来の処方を「漢方」と呼ぶのに対し、日本独自の処方を「和方」と呼ぶ。越後の毒消しは毒消丸と呼ばれる和方の薬で、菊名石(きくめいし)に硫黄(いおう)、白扁豆(びゃくへんず)、天花粉(てんかふん)、甘草が配合されている。当初「称名寺」という寺院で製造されていたことから「仏教は心の毒を消し、称名寺の薬は身の毒を消す」ともいわれた。毒消しという名前であるが、いわゆる有毒物の解毒や中毒の際に使う薬ではなく、気持ちが悪い時や食あたりの際に用いた薬である。
イシサンゴと硫黄が配合された処方
配合されている菊名石は菊目石、菊銘石、菊明石とも書くが、鉱物ではなく、イシサンゴの一種である。江戸時代の製薬家・遠藤元理がその著書『本草弁疑』で、菊目石を中国にはないと紹介している。生息地は紀州などの温暖な海で、新潟の海には産出しない。原料は大阪から仕入れていたと伝わる。
その他の生薬については、硫黄は内服としては下痢などに用いる。白扁豆は下痢や水腫、嘔吐、天花粉は熱病や口の渇き、甘草は鎮痛、去痰、解毒に用いる。かみ砕いて虫さされに塗ったという話が残るが、これは硫黄、天花粉を湿疹や癰(よう;皮膚のでき物)の塗り薬に配合していたことに由来すると考えられる。
ルーツは京都か
菊名石を用いた丸薬には、京都山科の有名売薬「金屑丸(きんせつがん)」があった。寺島良安著『和漢三才図会』の「菊銘石」の項には、金屑丸は食傷解毒の薬で、菊銘石は「酸ニ浸シ研末」、すなわち粉末とし、硫黄と合わせて金箔をかけた丸薬にしたとされる。そのルーツは、寺院同士のつながりで京都の金屑丸が北陸の寺院へと伝わったとも、当時普及した医学書『袖珍医便』に記載の処方を参考にしたのではないかともいわれている。
行商の盛衰
江戸時代半ばから製造販売の権利は寺院以外にも数か所あったが、幕末からは出稼ぎに行く大工が販売し、明治時代以降は男性に代わり、未婚の女性が新潟から遠く、関東方面まで半年以上行商に出向くようになった。このように長期にわたり遠隔地へと女性が行商に行くのは珍しい。販売していた薬は毒消丸だけでなく、近隣で仕入れた風邪薬や鎮痛薬、婦人薬などもあった。最盛期の大正時代には、2,000名以上の女性の行商人がいた。行商の稼ぎはその女性の小遣いとなるほか、生活費として家族に渡していたことで、家庭内での地位もほかの地域よりは高かったといわれている。
毒消丸の産地は土地が狭く農業ができず、主な産業は沿岸漁業と塩業であった。明治時代に塩の専売制が始まり、塩業が立ち行かなくなり、女性が行商に出るようになったといわれている。昭和に入ると薬事法改正に伴い、鑑札が必要となった。戦後も薬事法が改正され、処方の変更を余儀なくされ、行商での薬の販売ができなくなった。行商人も配置売薬や雑貨の行商人となったり、薬屋などへの転業が進んだ。
女性が支えた薬の行商
冬の寒い時期に作った薬を、暖かくなると行商に出かける。監督役の目上の女性と若い娘が売り子となって、「毒消しいらんかねぇ」「毒消し買わんかねぇ」と声をかけつつ売り歩いた。その姿を毎年楽しみに待っていた人も多く、堅実な商売から親戚以上の付き合いを持った相手もいた。家伝の薬はふつう、父から息子へと男性中心の一子相伝の形で伝えられるが、越後の毒消しは女性が製薬も販売も行うという形で、当時の村の一大産業に育て上げた薬であったといえよう。
| <参考文献> |
| 越後の毒消し |
小村弌著 巻町役場 1963 |
| 毒消村と呼ばるヽ十三ケ町村の調査 |
深見仁三郎著 [高志路2巻4号別刷] |
| 毒消し売りの社会史 女性・家・村 |
佐藤康行著 日本経済評論社 2006 |
| 日本の売薬(1-40) |
宗田一著 1冊 [医薬ジャーナル13巻1号-16巻4号 1977-1980別冊] |
| 日本の名薬 |
宗田一著 八坂書房 1993 |
| 中部の民間療法 |
杉原丈夫ほか著 明玄書房 1976 |
| 中国漢方医語辞典 |
中医研究院ほか編著 中国漢方 1980 |
|
|
 |
|

