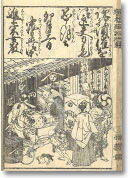 |
忙しい毎日とはうってかわり、お正月休みにはゆっくり読書を楽しんだという方も多いのではないでしょうか。新刊の紹介以外に、新聞の紙面には年間ベストセラーの本の紹介や話題の本の書評が目にとまります。本当にあらゆる本が次々と出版され、その数、種類も実に豊富ですね。
江戸時代の宝暦から天明期には、あらゆる出版分野で新しい企画が打ち出され、学問書、実用書、文芸書、版画などの刊行が相次ぎました。特にベストセラーとなった書籍は「千部振舞(せんぶふるまい)」と呼ばれて、1000部売れたら版元の人たちがそろって神社に御礼参りにいったといわれます。庶民は、書籍の値段が高価であったので買うことは難しく、貸本屋から本を借りて読むことが一般的でした。天保年間当時、貸本屋が江戸に約八百軒以上もあったとか。
今日では印刷技術の向上や流通経路の発達により、書籍を作ることや、流通させることはごく普通なことです。しかし当時は木版刷りで手作業であり、1000部を印刷・製本するには、かなりの労力が必要だったのではないでしょうか。江戸時代は古典や仏教書、医学書などを「書物」、浄瑠璃本、錦絵、通俗的な読み物を「草紙」と呼んでいました。取り扱うお店も書物は書物問屋で、草双紙は地本問屋と異なっていました。専門書を扱う本屋と町の売店のような本屋さんといったところでしょうか。
当時のベストセラーには井原西鶴『好色一代男』、近松門左衛門『曽根崎心中』、滝沢馬琴『南総里見八犬伝』、十返舎一九『東海道中膝栗毛』などがあります。このような印刷、出版物は日本全国に広く行き渡りました。地方の富農層の蔵書には教訓書にあたる本、例えば貝原益軒の『養生訓』『大和俗訓』『五常訓』などが必ずあったといわれます。ここからも人々の本に寄せる関心が強く、また庶民層にまで出版文化が根付いていたことがよくわかります。
何百年前の和装の書籍を、今も見ることができるのは感慨深いものです。昨年は電子書籍元年とも言われましたが、繰り返し出版され多くの人に読み継がれた書籍文化の良さを、改めて気づいた思いです。
|
|

