
|
 |
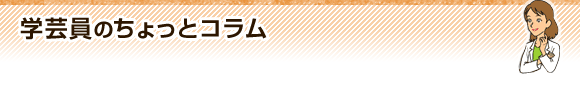 |
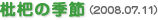
 |
|
|

みずみずしい果物や野菜が多く出まわる季節になりました。1月に白い花を咲かせた枇杷の木は、夏には鮮やかな黄金の実をつけます。昔、学校の校庭の片隅でたわわに実をつけた大木があり、その近くでよく遊んだことを思い出します。子どもたちが見上げるほど大きくて、上の方の実は高くて届きませんでした。大きなものは高さが10メートルにもなるようです。子どもの時はあまり好きな果物ではありませんでした。しかし、枇杷の実は甘さの中にわずかな酸味があって、今は大好きになりこの季節にはよくいただいています。
日本に渡来したのは9世紀頃で「大薬王樹」と呼ばれ、江戸時代には広く薬用として用いられるようになりました。『本草綱目』には咳を止め、気を下して熱を治すとあります。種は砕いて虫刺されなどの腫れ物に効能があるとされます。葉は乾燥させて煎じ薬にすると清涼、健胃などの薬になります。
京都と江戸では枇杷葉湯が暑気払いとして飲まれていました。枇杷葉湯は、枇杷・呉茱萸(ごしゅゆ)・莪朮(がじゅつ)・木香を中心に肉桂や甘草などを加えた薬用茶で、数種類の処方が見られます。枇杷には鎮咳・去痰・健胃作用、呉茱萸には健胃・駆風・利尿があるといわれるので、夏の暑さを防いだり疲れた身体をいたわる効果があったと思われます。江戸時代には喉の渇きを癒す清涼飲料として、枇杷葉湯売りが担い箱を担いで売り歩きました。その姿は夏を告げる風物詩でもありました。
また実をつけて薬用酒としても重宝がられました。果実で作った枇杷酒はストレートで飲んでも甘酸っぱい香りがあっておいしいく、カクテルにしても楽しめるようです。
暑い季節、果実を味わい薬草茶、薬用酒などを楽しみ、さわやかな気分ですごせたらいいですね。
|
|
|

