
|
 |
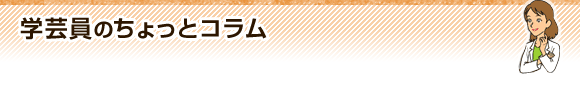 |
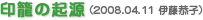
 |
|
|

印籠といえば水戸黄門の「葵の紋の印籠」を皆さん思い浮かべるのではないでしょうか。また「印籠と書くのに、どうして用途は携帯用薬入れであったのか」その起源についてはあまり知られていないようです。印籠は初め文字通り印判印肉の容器で、室町時代中国より伝わりました。その後宮中で公卿たちが火打ち石入れに使っていましたが、失火を恐れて火打ち石の殿中持ち込みが禁止されてから薬容器に転用されました。室町時代は唐物が珍重され、貴族の邸宅や寺院の書院の棚飾りに使われました。薬籠(薬箱)の代わりとして飾られた印籠が、やがて薬を入れる器の呼称として通用するようになったと推測されます。
それでは、重箱のような形の印籠が棚飾りから腰に提げる印籠となったのはいつごろなのでしょうか。はっきりとしませんが、近世初期の辞書や風俗画などが発生期を解明する手がかりを与えてくれます。例えば「十二カ月風俗図」(室町末から桃山初期の作1570〜1580)を見ると、印籠と巾着を腰に提げている人物が丁寧に描かれています。説はいろいろありますが、腰から提げる印籠は室町時代末期から桃山時代には用いられていたと思われます。桃山時代は風俗画、漆工芸、染色など工芸技術が進歩した時代でもありました。江戸時代の『萬金産業袋』にはさまざまな印籠について詳しく書かれていて、この頃の印籠は小型の容器を数段重ねたもので、蓋は印籠蓋のはめ込み式のため、薬の変質を防ぐ構造となっていることがわかります。
さらに江戸中期頃には実用性もさることながら、装身具としての役割が次第に強くなり愛玩品となっていきます。身分の高い人や富裕な人たちが趣味に応じて、蒔絵などの細工を施した意匠の凝ったものが造られるようになりました。そして美術工芸品として印籠や根付の評価が一層高くなり、欧米人に珍重されたため、国外へおびただしい数が流出したのは残念なことです。根付※はさしあたり今でいう携帯電話の高級なストラップといった感じだったのでしょう。携帯用薬入れとしての印籠は薬の品質保持のための工夫を、装身具としての印籠は繊細な工芸技術、日本の意匠着想の奇抜さ、表現の親しみや面白みなども伝えてくれます。
 |
※根付・・・江戸時代に煙草入れ、矢立て、印籠などを紐で帯から吊るし持ち歩くときに用いた留め具 |
|
|
|

