
|
 |
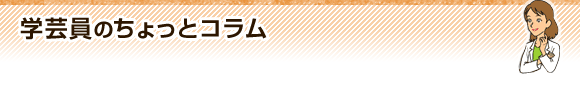 |
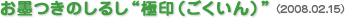
 |
最近、買い求める商品を選ぶときに迷ってしまいます。商品広告や包装デザイン、製造メーカーのブランド名にまどわされないようにと、包装紙記載の原料や原産地、製造年月日、製造者、製造方法などをじっくりと確認するものの、果たして信頼できるのかしら…。と疑わざるを得ない事件が多発しています。
いつの時代にも、私腹を肥やすために質や量を偽って取引しようとする人は現れました。古くは、安土桃山時代にさかのぼり、秤を改造するなど自分が得するようにごまかしました。
そこで、精密な秤が必要となり、信長をはじめ、秀吉、家康は卓越した技術を持つ職人に「天下一」という称号を与え、お墨つきを下した道具に「天下一」という誉れの極印を押すことを許可しました。
さらに1653年(承応2)、江戸幕府は「天下一」の称号を受けた東西二つの秤職人の専門集団、江戸の秤座「守随家」、京都の秤座「神家」だけに、桿秤の製造、頒布(販売)、検定、修理などを任命しました。秤は取引する上で互いの平等を確認し合う道具、正確な秤を使わなければ意味がありません。そうしたことからも正確な秤が重んじられた背景があるようです。
現在の計量法では、2年に1回、取引で使用する秤は定期点検が義務づけられていますが、すでに江戸時代から5年〜10年に一度は、所有する秤は秤改め(検査)を受けなければなりませんでした。そして検査に合格すると「極」「改」「定」など、その都度、形の異なる極印が、鞘、皿、錘にそれぞれ毎回1つずつ押されました。
今日の認定マークは、政府の諸官庁からさまざまなものが発行されています。しかしながら、ごまかしや不正などが横行して、お墨つきの印の信頼も失われつつあるようです。「極印を押される」とは、良い認定印だけでなく、悪い烙印という意味もあります。ダメな奴だと押されるのも「極印」、消すことのできないダメ印を一度刻印されてしまうと取り消すことは容易ではありません。極めた証の極印であってもらいたいと願います。
|
|
|

