
|
 |
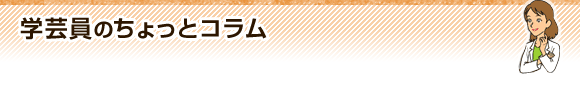 |
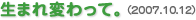
 |
|
|
叔母の着物を形見分けする、という話があった時に、分けてもらう私たちは「体格も年齢も違うから、着られないものだったらどうしようか?」と少し心配していました。ところが伯母の娘、つまり私の従姉は器用にも何枚もの着物をほどき、端布(はぎれ)にしてパッチワークの手提げ鞄を作ってくれました。よく見ると、「ああ、この着物は旅行の時に着てた」などと見たことのある布ばかりでした。
叔母自身もお針が得意で、風呂敷を帯にしてみたり、手提げを自作したりしていたので、従姉にもその気持ちが伝わったのでしょう。叔母も今頃、空の上で喜んでいると思います。
着られなくなった和服が一枚の布に還り、また別のものに生まれ変わる。その手提げ鞄は、なんだか叔母その人が生まれ変わったような気がしました。
最近、もったいない、という言葉が社会全体で重要なキーワードになってきています。博物館では、今年からゴミの分別を更に徹底し、リサイクルできるものはリサイクルに回し、あわせてゴミの排出量を減らすように努めています。また、職員が不在の事務スペースの電灯はこまめに消灯するなど、電気使用量も減らす努力をしています。このように、目に見えるものであれ、エネルギーであれ、大切にしなければ、という義務感ももちろん必要です。ただ、その一番底にある、ものを慈しむ心というものを忘れずにいたいな、とつくづく思いました。
|
|
|

