
|
 |
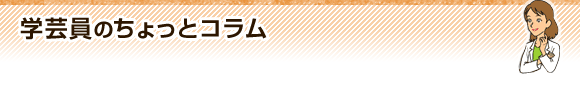 |
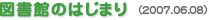
 |
|
|
中国では、古く周の時代(紀元前11〜3世紀)に、蔵書の制が始まったといわれます。日本では、唐の制度を輸入して発布された大宝律令(701年)によって設けられた「図書寮」が、図書館ということばと重なりますが、経籍・仏像の管理の他、紙筆墨の製造供給、写経・書写などを行う役所であったようで、今の図書館に近いものはもっと後にならないと見られません。もっとも「館」よりも、「文庫」「文倉」「亭」「楼」などのことばが用いられたようです。
文庫はどちらかというと公開するよりも蒐集を意味し、書籍を収めておく倉をさしているようです。蔵書、コレクションそのものや、それを収める施設をさす語として用いられるようになりました。大名や藩校のもとには優れた文庫があります。
明治中期には訳語で図書館(ずしょかん)が登場します。図書・記録、その他の資料を収集・整理・保管し、必要とする人の利用に供する施設でした。
また、近世の文庫から引き継がれた蔵書を基礎として、国立国会図書館の源流である書籍館(しょじゃくかん)、国立公文書館に統合された総理府の内閣文庫などがありました。中には有力者の私的なコレクションから出発し、今日は利用に供するようになった所もみられます。
図書館の歴史から昔の暗くて湿っぽいイメージもっている人がいるかもしれません。しかし、最近は明るく自然光が差し込むロビーがあったり、高い吹き抜けがあったりし、建築上からみてもすばらしいデザインの建物も各地にみられるようになりました。また、図書館によって蔵書の傾向に特色があります。例えば、地域の情報を得たいならば、その土地の図書館を実際に訪れたり、お問合せをしてみるといいかもしれませんね。
|
|
|

