
|
 |
 |
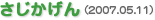
 |
江戸時代の医師は、一般には刀圭家(とうけいか)、将軍家や大名などの侍医、御典医は、お匙(おさじ)と呼ばれていました。これは江戸時代の漢方医が、薬を調剤するときに「薬匙」を扱う姿を、周囲の人々には頼もしく映ったことに由来する呼称です。
そもそも「薬匙」とは、固形薬物または粉末薬をすくって調合する匙で、大小さまざまな大きさと形の種類がありました。丸剤の粒数を数えるものに計粒匙というものもあります。材質は金属、あるいは動物の牙や角や、木製などからできていて、日常的には丈夫で錆が生じ難い真鍮製、金、銀、銅(近年ではステンレスやプラスチック)の製品を用いました。しかし、金属に触れて変化する薬物を扱う際には、牛角や象牙製のものを使用していました。
道具としてだけでなく、その微妙な調整技術を含めて「匙加減」という言葉が多用されるようになりました。もともとは、匙ですくう薬の多少を「匙加減」と言いました。患者を生かすも殺すも、この待医の「匙加減」一つで決まったことから派生して物事を扱う場合の状況に応じた手加減、手心の加え方を表す意味としても広く使われています。
さらに「匙を投げる」とは、医者が匙を投げ出すことから、患者に治る見込みがないと診断して治療を断念することです。物事の見込みがないとあきらめて、これ以上やってもしょうがないと見放す意味で使われるようになりました。
匙を使って薬を盛る医師の技術は、この他にも「匙先」「匙執り」など、さまざまな言葉で表されていて、微妙な匙加減は、医師の大切な技術だったことがよくわかりますね。
※人と薬のあゆみ『医家で往診先で使用された道具』
|
|
|

