
|
 |
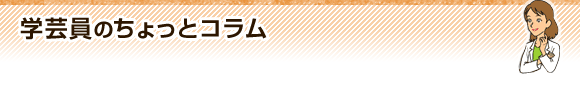 |
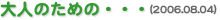
 |
|
|
ときどき私は、あてもなく本屋さんをぶらぶらして立ち読みするのが好き。そんな時に、平積みに並べられた大人のための書籍コーナーに目がとまりました。ぬり絵やドリル、楽しく取り組めそうな本がたくさん出版されていました。私もやってみたい!そんな気持ちになりました。ぬり絵は、子どもの頃を思い出しながらできるため、「楽しくて、頭がすっきりする」と好評のようです。脳の働きがよくなるとか、リラクゼーション効果もありますよね。
このように、大人がぬり絵をしたり、鉛筆でなぞり書きをする本が、ここ最近のブームとなっています。この現象、そもそもは『脳を鍛えるドリル』や、『声に出して読みたい日本語』などの、脳の活性化を促すような本が火付け役となっているようです。
そして、ぬり絵の次に企画出版されたのが、なぞり書きの本、『えんぴつで奥の細道』『えんぴつで百人一首』など、文字を書くタイプの本です。小学校の国語の授業で書き方の練習帳に、「あいうえお」などと書いて覚えた懐かしさと通じるものがあるようです。写経のような感覚で、昔に暗誦した「月日は百代の過客にして行かふ年も又旅人也」といった名文を一文字ずつ書いていくことで「心が平安になる」といった感想もあるそうです。薄く印刷された文字をえんぴつでなぞりながら、元禄2年(1689)3月27日から9月6日までのひと夏に、深川(東京都)、草加、千住、粕壁・・・、そして最終地の大垣(岐阜県)までの地を、松尾芭蕉(1644−1694)と一緒に旅しているような気分になれるのも特徴です。
内藤記念くすり博物館でも、文化12年(1825)に出版された180年前の『奥の細道』を所蔵しています。こうした本の出版ブームによって、古典も身近なものに感じられることでしょう。今後は『徒然草』や『万葉集』なども出版される計画があるそうですし、文字をなぞりながら、古典の世界を親しめるというのも味わい深くて楽しいですね。
|
|
|

