
|
 |
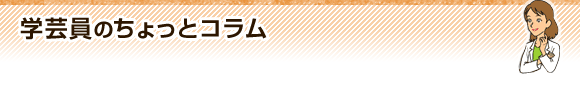 |
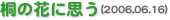
 |
|
|
桐の花を見るといつも思い出す光景があります。大学生の頃、名古屋の市バスに乗って徳川美術館に行く途中のことです。その途中のビルが立ち並ぶ道沿いに、大きなお寺があってその庭に桐の花が満開に咲いていました。白い壁で覆われた敷地の外からもあふれんばかりの花を見ることができました。空に広がる薄赤紫の花の鮮やかさが強く印象に残っています。まわりはトラックやバスや乗用車がひっきりなしに通る喧騒さとは反対に、その景色だけがひっそりと静まりかえっていました。
桐は落葉広葉樹で大きく育つと高さ10メートル、直径1メートルにもなります。塀よりも高く枝をのばして花をびっしりつけるため、その見事な花々は道行く人々の目を楽しませてくれます。
優れた特徴が多いことでも知られます。銀白色か褐色をおび、つやがあり軽くて木目が美しく材質がやわらかく狂いが少ないといわれます。また湿気を吸わず熱の伝導性も少なく燃えにくいことから、箪笥、琴などの楽器、仏壇、建築、彫刻などの材料として古くから用いられてきました。
そうそう博物館にもそんな桐製の薬箪笥や薬箱があるのですよ。生薬をいれるためにたくさんの引き出しがあるので、百味箪笥といわれます。江戸時代に作られた百味箪笥の金具がはずれていることはあっても、実にきちんと作られています。小ぶりなものはアンティークなインテリアにもなりそうです。
また、桐は鎌倉時代の末には天皇家の紋章として定着しました。「五七桐」は菊と並んで皇室の紋章ですし、足利家、豊臣家も桐を紋章としています。徳川時代は禁木で保護を与えた藩もあったようですね。
「桐一葉落ちて天下の秋を知る」は中国の古典『淮南子』に由来するといわれます。豊臣政権の五奉行の一人の片桐且元が、淀君に疎まれて解任された時に自らの運命を自嘲して、また豊臣政権の行く末を案じての句としても知られます。後世、木の葉一枚のささやかなたたずまいから、大きな時代の動きを察するという人間の洞察力を象徴する名句として親しまれています。
あの大きな桐の葉が風もないのに地上に散ると、ずっしりとさまざまな思いの重さが伝わるような気がします。
※人と薬のあゆみ「薬箱、往診用百味箪笥」
|
|
|

