
|
 |
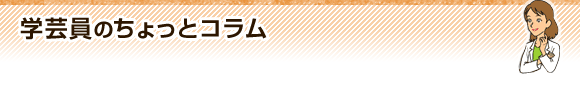 |
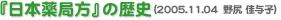
 |
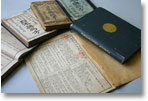 |
初版『日本薬局方』:
明治19年6月25日公布 |
|
薬局方は、薬剤師にとってバイブルのようなもの、必要不可欠な医薬品の情報が記された馴染み深い公定書であり、世界主要各国(あるいは数カ国共同)がそれぞれの薬局方を発行しています。
我が国の『日本薬局方』は、薬事法によって医薬品の性状及び品質の適正を図るために、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定めた医薬品の規格基準書として、通則、製剤総則、一般試験法及び医薬品各条からなり、繁用されている医薬品が収載されています。
最新版は、平成13年3月30日に公布された第十四改正ですが、明治19年(1886)6月に初版が公布されて以来、医薬品の開発、試験技術の向上にあわせて内容の改訂がくりかえされてきました。
最初の『日本薬局方』は、お雇い外国人の化学者ゲールツらの指導によってドイツ薬局方、オランダ薬局方を参考に作成されました。海外から、不良品、粗悪品などを含むさまざまな品質規格の医薬品が大量に輸入され、品質を統一する基準が必要になったためです。
くすり博物館では、稀少な119年前の初版『日本薬局方』を保存しています。明治19年6月25日の官報第894号別冊内務省令第10号の官報に掲載されたのが最初ですが、[欧米各国局方対照][音釈付][註釈]などを掲載したものや、ラテン語に翻訳された薬局方もあります。
こうした『日本薬局方』の発布は、明治憲法発布に先立つ3年前のことで、近代的スタイルのものとしては、東洋では最初、世界では第21番目の国定薬局方でした。
そもそも「薬局方」という名称、Apotheek(オランダ語)、Pharmacopoea(ラテン語)、英語では、Pharmacopoeia(英語)、Pharmacopeia(米語)、ですが、語源はギリシャ語の「薬」と「作り方」に由来するといわれています。
日本語の「局方」という独特の名称がなぜ、「公定薬典」ではなく「局方」なのか。また、「法」とせずに「方」の字を用いたのかと不思議に思う方もいますが、江戸中期、蘭方医中川淳庵が オランダの薬局方「アポテーキ」を「和蘭局方」と訳したのが、書名での最初の使用といわれています。
さらに起源を遡ると、中国宋代(1078-85)に刊行された協定処方集『(太平惠民)和剤局方』に倣ったものだとされています。『和剤局方』は、日本にも平安末期に伝わり、漢方製剤の適応症、薬剤名、処方量、調製法、用法用量などについてが詳述されていて、現在の薬局方のような書物として江戸時代から明治初期に利用されていました。
※全ページをデジタルアーカイブでご覧いただくことができます。
 |
|
|

