
|
 |
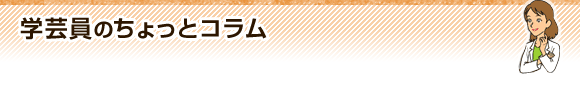 |
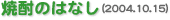
 |

|
ここ数年ほど、焼酎ブームが続いていますね。私も焼酎は大好き!大きめで柔らかい梅干の果肉を少しずつつまみながら、お水で薄めないオンザロックを、キリッといただくのが好みです。米や麦からつくられたものも、芋や黒砂糖、またはとうもろこしなどを原料としたもの、どれもそれぞれに美味しいですね。
少し前までの焼酎には、アルコール度数が高くて、安価なお酒というイメージがありましたよね?そんな風に父や祖父からは聞いています。しかし最近は、入手困難な幻の焼酎と呼ばれるプレミア焼酎が話題になったり、おしゃれな焼酎バーも見かけるようになりました。
また、果物や生薬を漬け込んで作られた果実酒や薬用酒は、純度の高い焼酎(甲類:ホワイトリカー)をベースにして作られています。胃腸や暑気あたりにいいとされる梅酒や、咳止めのカリン酒などは、甘酸っぱくて美味しい飲み物というだけでなく、薬代わりとしても好まれる身体にいいお酒です。
そもそも焼酎の起源は、紀元前のエジプトで製造された蒸留酒にまで遡ることができます。蒸留器「アランビック」で製造されました。この蒸留器、日本には蘭方医学とともにポルトガル経由で伝わり、江戸時代には「ランビキ(蘭引)」という名称で陶器製のものが普及しました。アランビックという言葉が変化して、ランビキと呼ばれるようになったそうです。蒸溜技術がいつ頃日本に伝わったかは、はっきりとしていませんが、少なくとも500年前に、焼酎が飲まれていたことを示す古文書が南九州で発見されています。
そんな焼酎、古くはアルコール飲料としてだけでなく、医療用の消毒薬としても重宝しました。度数が高いため傷口を消毒するための貴重な薬でした。スポーツや野外キャンプなどでけがをした時に、緊急用として役に立つかも?!アウトドアの知識として覚えておくと、いざという時には便利で頼もしいお酒ですね。
こうした蒸留酒やランビキの起源、昔の医療文化に思いを馳せながら飲む焼酎は、時代をタイムスリップして、心地よい酔いに包まれる気がします。
● 人と薬のあゆみ『海を渡って』 >>
|
|
|

