
|
 |
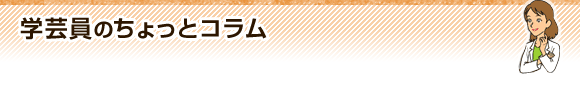 |
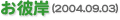
 |

|
日中は照りつけるような暑さでも、朝晩は随分秋らしくなりました。それでもあっという間にお彼岸ですね。
さて、お彼岸といえば何を思い浮かべますか?お墓参り、お線香、和菓子の「おはぎ」・・・。私はやはり「おはぎ」でしょうか。『和漢三才図会』に「牡丹餅および萩の花は形、色をもってこれを名づく」とあり、牡丹餅が「ぼたもち」になり、萩を丁寧に言って「おはぎ」になったといわれます。小豆をまぶしたところが牡丹の花に似ているという説もあります。また、ぼたんの他にも、ぼたもちの名の起りを仏教に求める説や、おはぎは宮中奉仕の女官が用いた女房詞(にょうぼうことば)に由来するという説など色々あるようです。定説に従えば、春は牡丹、秋は萩となり、同じお彼岸でも春秋使い分けないといけないのかもしれませんが、近年は年中「おはぎ」で通すことのほうが多いようです。
また、この季節が近づくと群生して咲く真っ赤なヒガンバナを、田園や川原などでよくみかけるようになります。私は、こどもの時にこの赤い花を家に持ち帰ると火事になるといわれた記憶があり特別な花という気がします。
ヒガンバナは、各地でさまざまな呼び名がつけられてきました。マンジュシャゲという別名は多くの方がご存知かと思います。日本では秋分の日前後の1週間を「秋のお彼岸」と呼び、先祖の墓にお参りをする風習がありますが、ちょうどその頃に咲く花なので、ヒガンバナと呼ばれるようになったようです。
「日本植物方言集(草本類篇)」には、ヒガンバナの地方名として約400もの名があげられています。その中には、葉と花が同時にないことを示すハミズハナミズ(青森県など)、花の形に着目したチョーチンバナ(神奈川県など)、墓地によく見られることから連想されたと思われるシヒトバナ(宮城県など)、花の見ための様子からヒマツリ(滋賀県など)、有毒なことを表現したドクバナ(群馬県など)、食用にしたことを示すと思われるシロイモチ(徳島県)など、さまざまな性質に着眼してつけられた名前があり興味深いものです。
ヒガンバナの花をよく見ると、一つ一つの花は大きく反り返った6枚の花びらからできています。花の中心からは7本のしべが伸びており、先に小さなTの字型の葯(やく)※がついているのが雄しべで、6本あります。その部分のない1本が雌しべで、中央に位置しています。日本のヒガンバナの場合、実を結ぶことがありません。それは、日本にあるヒガンバナが、種なしスイカと同じように三倍体(さんばいたい)という性質のものだからです。中国には実を結ぶ系統のものもあり、ヒガンバナのふるさとは中国だろうと考えられています。
おはぎもヒガンバナも私たちを郷愁にひたらせるものですが、いろいろ調べていくと面白いことがわかってきますね。故郷が遠くにある人も近い人も、身近なものをよすがに気持ちだけでも故郷へ帰ってみるのもいいかもしれません。
※花粉を入れるところ
-参考図書- 「日本植物方言集成」八坂書房編 2001/八坂書房
 |
|
|

