
|
 |
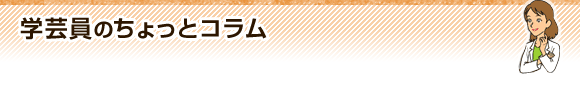 |
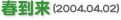
 |

|
新年度を迎え、町には真新しいスーツや制服をきたフレッシャーズがあふれていることでしょう。博物館や薬草園も製薬会社や卸の会社の新入社員研修や小学生から大学生まで団体で来館され、とてもにぎやかになります。4月は入園、入学、入社、転勤・・・多くの出会いと別れが繰り広げられます。日本では、新年度の4月始まりが明治時代より今も続いていますが、桜が咲いて芽吹く季節が実にぴったりだと思います。
博物館は木曽川の中洲にあり、近くの堤一帯には、山桜※や枝垂れ桜などがみられる「桜の里」があります。道路を囲む形で桜並木のトンネルができているため、なかなか見ごたえがありますよ。桜並木の木の根元には若草が生え、可憐な花も多く、気をつけてみると薬草もちらほら見られます。昔は草花をつんだり花輪などを作ってよく遊びました。今でもこういったところを散歩すると、わくわくして、とても楽しい気持ちになれます。
ところで、この桜、特に山桜は江戸時代の出版物を刷る版木に多く用いられていました。たくさん刷っても磨り減らず丈夫であり、木版印刷に適した木材でした。現在でも博物館で、木版刷りで製作された浮世絵※、和装本※、薬袋などを見ることができます。
また、この季節、気候の変化が激しく花冷えというように、肌寒く強い風が吹いて花吹雪になることがあります。昔の人々は病気の精霊が花びらに乗って飛び散るので、疫病がはやると考えました。この時期に悪疫退散を祈り、病気を鎮めるための鎮花祭(はなしずめのまつり)が行なわれるようになったのでしょう。
満開の桜も素晴らしいですが、私は逆に、疫病がはやる前触れといわれた「花びらが散りはじめる時」がもっと好きです。花が散るのと一緒にインフルエンザなど悪い病気もおさまってくれるといいと思うこの頃です。
● 浮世絵(錦絵) >>
● 浮世絵(錦絵) >>
● 和装本 >>
● ソメイヨシノ >>
● ヤマザクラ >>
|
|
|

