
|
 |
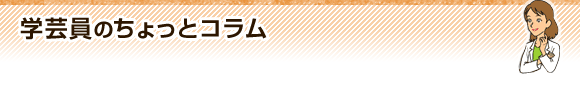 |
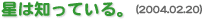
 |

|
久しぶりといえば、あまりに久しぶりに行ってきました。プラネタリウムに。
きっかけは東海三県の博物館の集まりで、ある科学館の学芸員の方にたずねられたことです。「プラネタリウムって、最後に行ったのいつでしたか?」くすり博物館の学芸員として、医薬や科学史、薬草や植物などの展示には結構目を光らせていたのですが、プラネタリウムは・・・盲点でした。
川島町近辺は幸い高い建物がなく、残業帰りに薬草園の脇で空をあおぐと、街灯に邪魔はされますが、比較的よく星空が見られます。真冬の風が強い夜や、正月・お盆など車が少ない日は特にきれいに見えます。そのせいでしょうか。わざわざプラネタリウムまで行くまでもないかも・・・と思い込んでしまったのは。
岐阜市科学館のプラネタリウムが残念ながら工事中だったため、足を伸ばして名古屋市科学館へ行きました。こどもの頃に来た時は、星空を投影するドームの下辺に名古屋の街並みが切り絵で表されていて、そこが赤く夕焼けに染まるところから始まったような記憶があります。現在はパノラマ画像で街並みが映し出され、通常の星座の説明が終わると、なんとニュートリノのお話※が始まりました。このような現代の宇宙に関するプログラムは名古屋だけでなく、四日市など各地のプラネタリウムで行われています。学校向けの授業ではなく、大人もこどももプラネタリウムを楽しみ、宇宙に親しんでもらえるようにという取り組みなんだそうです。
周囲には家族連れも多く見られましたが、時々親子で小声で話す以外は、みな熱中して星空を見上げていました。
私もオリオン座くらいはなんとか覚えていました。しかし、アルデバランやカペラなどの個々の星の名前や、火星・土星の現在位置などは、丁寧に説明してもらってやっと思い出したり理解するありさま。昔はこれでも星座にまつわるギリシア神話とか、ロマンチックな伝説を読みふけった口なんですけどね。
また、ニュートリノなどの新しい事柄についても、新聞で読んで結構理解していたつもりだったのですが、なぜ、カミオカンデの大きな水槽が必要だったのか、あの水槽でどんなことが起きたのか、図入りで説明してもらうと納得しきり、でした。
そのほか、お話では、名古屋の市街地と信州の山の中での星の見え方を比較し、空気だけでなく“光害”などの環境問題にもふれていました。プラネタリウムはただ星空を映すのではなく、人間のいろいろな営みも映し出していたんですね。地上からは見えないものも、星空からみたら見えるのかもしれません。私はどんな風に見えるのでしょう?・・・せめてプラネタリウムの星に聞いてみたい気がします。
※2004年1月のプログラム。毎月変わります。
● 名古屋市科学館『天文情報』 >>
● 四日市市立博物館『プラネタリウム』 >>
● 岐阜市科学館 >>
 |
|
|

