 |
 |
 |
 |
 |
 |
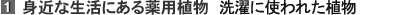 |
 |
 |
 |
洗濯物を洗濯機に放り込み、洗剤と柔軟剤、漂白剤なんかを所定の場所に入れてスイッチを押すだけ。いい洗濯機ならば、乾燥まで一気に仕上げてくれます。私たちの母や祖母の世代の家事からすれば、労働としての洗濯は格段に簡単になりました。
では、その昔はどのように洗濯したのでしょうか。日本では川や井戸水でもみ洗いやふり洗い、そして着物の時代になると、伸子張り・板張りにより洗濯しました。ヨーロッパやアジアの一部では、昔は川の岩の上などで踏み洗いをした地域もありました。特にヨーロッパでは、羊毛を用いた衣服が作られるようになり、毛についた汚れはなかなか落ちにくく、白土や腐らせた尿を脂汚れ落としに用いたこともあったそうです。
やがてリネンや木綿などの織物が登場すると、泡立つ植物で洗濯したり、洗濯板を用いたりするようになりました。その後、草木の灰汁と動物脂から軟石鹸が作ら
れ、さらにオリーブ油と海草を焼いた灰から作る硬石鹸が作られるようになりました。石鹸はアルカリと脂肪酸から出来ており、化学的な方法で作る技術が考案され、現在に至っています。
サボンソウの根を切ったものと水を容器に入れ、振り混ぜると確かにたくさん泡が生じます。少量泡立てて鉛筆で汚したガーゼを洗ってみましたが、今回はきれいになったとは言えませんでした。それでもサボンソウの英名は、Common Soapwort、Bouncing Betで、別名にも洗い張り屋の草(fullers herb)、泡の出る根(latherwort)、カラスの石鹸(crow soap)、石鹸の根(soap root)とあるくらいですので、昔は頼りにされていたのでしょう。
ムクロジの果皮ではたくさん泡が立ちましたが、汚れが落ちるというほどではありませんでした。かつてはこれで洗濯していたのかな、と考えると、いまさらながら昔の労働の大変さが身にしみました。
記事:内藤記念くすり博物館
稲垣 裕美 (2008年8月) |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 【ヨーロッパ】 |
○サボンソウ(Saponaria officinalis L.)
・・・根を乾燥させたものをサポナリア根といい、梅毒・皮膚病の薬とした。
・ナデシコ科センノウ属の一種(lychinis flos-cuculi)
・ナデシコ科マンテマ属の一種 |
| 【アメリカ】 |
・アカザ科アカザ属の一種(Chenopodium californicum)の根
・ムクロジ科ムクロジ属(soapberry)
○ムクロジ(Sapindus mukorossi Gaertn./Soapberry、Chinese soapberry、Soapnut Tree)
・シャボンノキ(Sapindus saponaria L./Soap Wood Tree、 Soapberry、Soap Tree)
○ナンキンハゼ(Sapindus sebiferum L./Chinese Tallow Tree)・・・油脂を石鹸に利用 |
| 【アフリカ〜アジア】 |
・ハマビシ科の一種(Balanites aegyptica L.)
・・・果実のパルプ質を食用にするほか、絹の洗濯に使用されたとされる。
種子の黄色の油は石鹸製造に適するといわれる。 |
| 【日本】 |
サイカチ・・・果皮のさや(ソウキョウ)を石鹸の代用とした
ムクロジ
トチ・・・実を利用
※草木の灰汁も利用した |
|
<参考文献>
ハーブ&スパイス サラー・ガーランド著 福屋正修訳 誠文堂新光社 1982
世界有用植物事典 掘田満ほか編 平凡社 1996
せんたくのはなし 津田妍子著 さ・え・ら書房 1986
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |

