 |
 |
 |
 |
 |
 |
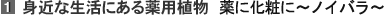 |
 |
 |
 |
クラシックに「野ばら」、シャンソンに「ばら色の人生」という唄があるせいでしょうか、私はバラの原産地をヨーロッパだと思っていました。ところが調べてみると、園芸種のバラはヨーロッパで盛んに作られていますが、野生のバラの故郷は西アジアから中国にかけての地域ではないかといわれています。日本でも『万葉集』に宇万良(うまら)という名で、野性のノイバラと思われる植物が詠まれています。
漢方医学でも、さまざまなバラの仲間が営実(エイジツ)、金桜子(キンオウシ)、郁李仁(イクリニン)、 瑰花(マイカイカ)といった生薬名で利用されてきました。営実はノイバラの成熟した果実で、下剤・利尿薬として用います。テリハノイバラの実も含まれることがあるようです。金桜子はナニワイバラの果実で、強壮や下痢止めに用います。郁李仁はニワウメやユスラウメなどの種子とされますが、日本の本草学者・小野蘭山はニワウメとしています。便秘・浮腫などの際、緩下剤・利尿薬として用いられました。 瑰花(マイカイカ)といった生薬名で利用されてきました。営実はノイバラの成熟した果実で、下剤・利尿薬として用います。テリハノイバラの実も含まれることがあるようです。金桜子はナニワイバラの果実で、強壮や下痢止めに用います。郁李仁はニワウメやユスラウメなどの種子とされますが、日本の本草学者・小野蘭山はニワウメとしています。便秘・浮腫などの際、緩下剤・利尿薬として用いられました。
|
|
 |
日本では、大同3年(808)に勅命により編纂された医書『大同類聚方(だいどうるいじゅうほう)』に、ノイバラの実の「牟波良美(むばらみ)」という名前が見られます。延喜18年(918)には、『本草和名(ほんぞうわみょう)』に「営実 一名薔薇(しょうび) 和名宇波良乃実(うばらのみ)」が登場しています。これ以降バラの仲間は、貝原益軒の本草書『大和本草』をはじめ、江戸時代の園芸ブームの折には『花壇綱目』などでたびたび紹介されました。日本では民間薬としてノイバラを用いる際には、中国医学とは異なり、まだ青みが残る果実を日干しにして利用したそうです。
|
 |
| 木曽川河畔のノイバラ |
|
江戸時代の美容書『都風俗化粧伝(みやこふうぞくけわいでん)』には、ノイバラの花を蒸留した“花の露”に丁子(チョウジ)や白檀(ビャクダン)の香りをつけた化粧水が登場します。この本には、“花の露”が“香薬水(においくすりみず)”として肌につやを出し、匂いをよくし、きめ細かくする上、顔の腫物にも効果があると書かれています。使用方法は化粧した後に刷毛で顔に塗るもので、今でいうところの薬用化粧水でしょうか。市販された“花の露”もありましたが、火鉢に“らんびき”という蒸留器、もしくは薬缶(やかん)と茶碗で作った簡易な蒸留装置で作る方法も紹介されています。
西アジアから北アフリカでもバラの種類こそ異なりますが、花びらを蒸留して作ったローズウォーターを美容に使います。ヨーロッパでは、芳香の強いダマスクローズを香水に使用してきました。蒸留という技術は西アジアで発達したものですが、その技術が西はヨーロッパ、そして東は遠い日本へも伝わったおかげで、江戸時代の女性たちも化粧水を作ることができました。蒸留の難しい原理はさておき、たとえ精油まじりの水程度のものであっても、自分で蒸留して化粧水を作るのは楽しそうですね。
ローズウォーターは地域によっては料理に使いますし、花びらを乾燥させたローズレッドや、ドッグローズの実であるローズヒップはハーブティーにもします。バラは「見る」だけでなく、「使う」植物でもあったのですね。
記事:内藤記念くすり博物館
稲垣 裕美 (2012年6月) |
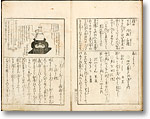 |
| 『都風俗化粧伝』らんびきの図 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| ノイバラ |
 |
イクリニン |
 |
| <参考文献> |
| 週刊朝日百科世界の植物 |
朝日新聞社 1975-1978 |
| 世界有用植物事典 |
平凡社 1989 |
| 原色牧野和漢薬草大図鑑 |
三橋博監修 北隆館 1988 |
| 原色和漢薬図鑑 |
難波恒雄著 保育社 1980 |
| 薬草カラー大図鑑 |
伊沢一男著 主婦の友社 1992 |
| 都風俗化粧伝[東洋文庫] |
佐山半七丸[著] 速水春暁斎画 高橋雅夫校注 平凡社 1982 |
| やまと花万葉 |
中村明巳写真 片岡寧豊文 東方出版 1992 |
| 万葉の植物[カラーブックス] |
松田修著 保育社 1966 |
| 中国本草図録 |
蕭培根主編 中央公論社 1993 |
| 中国の花ことば 中国人と花のシンボリズム |
中村公一著 岩崎美術社 1990 |
| ローズビューティブック |
伊藤緋紗子著 フォーシーズンズプレス 2008 |
| 魅惑のモロッコ[地球の歩き方gemstone026] |
たかせ藍沙編 ダイヤモンド社 2010 |
| からだに効くハーブティー図鑑 |
主婦の友社 2008 |
| 日本のバラ |
松本路子写真 大場秀章監修・文 淡交社 2012 |
|
|
 |
|
 |
 |
 |
 |

