 |
日本の和紙は、強さとしなやかさを兼ね備えた紙として定評があります。文書や経典などの記録紙として和紙を使い始めたのは1300年前のことです。和紙は丈夫で長持ち、カビや虫食いなどに注意してきちんと保管できれば、1000年以上残ることが既に証明されています。
和紙の原料となるのは、植物の繊維、主としてコウゾ、ガンピ、ミツマタなどの樹皮が用いられています。作り方は(1)水につけた樹皮を煮て精製します。(2)川や雪などにさらして漂白します。(3)そして紙を漉く作業。(4)最後に板上に広げて天日で乾燥します。こうした工程を冬の寒い季節に手作業でおこなうことによって、上質な手漉き和紙が出来上がります。
原料として最も多く使用されているのは、クワ科のコウゾ(楮)から作られた楮紙(こうぞがみ・ちょし)と呼ばれる和紙です。繊維質が多くて紙質は荒いが強くて丈夫、日当たりがよい場所で栽培することが容易なため、和紙全体の9割を占めます。岐阜県美濃市では良質のコウゾが収穫されて、すばらしい障子紙や記録紙と定評のある美濃和紙が伝統的に量産されています。
ジンチョウゲ科のガンピ(雁皮)は斐紙とよばれる和紙で、繊維が短く緻密なため薄くてスベスベした光沢のある和紙になります。野生でしか育たず栽培に向いていないため、希少な高級紙とされています。ジンチョウゲ科のミツマタは湿潤な場所によく育ち、丈夫なのでお札や証券用紙などに使われています。
そして、これらの紙の繊維をつなぐための糊のような役割として、トロロアオイやノリウツギなどが使用されます。
和紙は古来、行灯や提灯などの照明器具、涼風を運ぶ団扇や扇子、雨を凌ぐ番傘、部屋を仕切る障子や襖や衝立など、日本人の暮らしの中で使われてきました。柔らかい触感や墨で書いた時のしっとりとした味わいなどは、独特の癒しの効果があるように思えます。そのためでしょうか、今ふたたび、美しい和紙は和風モダンテイストのインテリアの中にも見直されているようです。
記事:内藤記念くすり博物館
野尻 佳与子 (2006年10月)
|
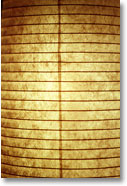 |
 |

