 |
ついこの間まで冷たい風の中を歩いていたのに、気がつくと春はそこまでやってきています。
私のウォーキングコースのひとつに、住宅地を抜けて堤防にあがり、そこから公園や神社へ向かうルートがあります。その住宅地の家々には、生垣を作られている家がいくつかあります。年末に剪定された生垣は、冬の間ちょっぴりくすんだように見えましたが、暖かくなり始めると、つやつやと輝いてきました。
かつて家の垣根は、竹を組んだり、柴を編んだりした低いものが多かったように思われます。『徒然草』にも透垣(すいがい)として、板や竹で垣根を作る時に間をあけ、中が透かして見える程度に組んだ垣根が登場します。しかし、近年ではプライバシー保護や防犯の観点から、ブロック塀にしたり、背の高い木を植えたりすることも多いようです。洋風建築の垣根には、コニファーを使ったり、つる植物をトレリスに這わせて垣根にしている家もあるようですね。
また、米沢市にはウコギの垣根が多いのですが、これは、江戸時代の藩主・上杉鷹山(ようざん)が奨励して作らせたといわれています。春から初夏の新芽が食用になるため、垣根と食用の一石二鳥、というところでしょうか。
垣根は、“内”と“外”を隔てるものですが、外壁というほどには“外”をシャットダウンしている訳ではありません。“垣根越し”に隣家の人と会話をかわしたり、食べ物のおすそ分けをする光景は、かつては珍しいものではありませんでした。また童謡の「たき火」でも、垣根のある風景が唄われています。そんな垣根は、向こう側をひょいとのぞきこむと、誰かと話ができるちょうどよい距離を保つもののような気がします。
記事:内藤記念くすり博物館
稲垣 裕美 (2010年3月)
|
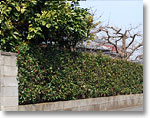 |
 |

