 |
 |
 |
 |
 |
 |
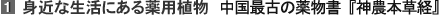 |
 |
 |
 |
中国最古の薬物書に『神農本草書(しんのうほんぞうきょう)』があります。“神農”とは4000〜5000年前と言われる古代中国の神で、身近な草木の薬効を調べるために自らの体を使って草根木皮を嘗め、何度も毒にあたっては薬草の力で甦ったといわれています。こうして発見した薬によって多くの民衆が救われ、神農は薬祖神として祀られるようになりました。
『神農本草経』は、神農がまとめた書物ではありませんが、こうした伝説にあやかって書名がつけられたようで、古代中国に伝わる薬物の知識が集録されています。編者だけでなく成立年代も定かではありませんが、一般的には1〜2世紀頃といわれています。原本は古くに散逸してしまいましたが、後の陶弘景(452−536)が500年頃に著した書物に引用したので内容が残り、それをもとに近世になってから充実した復元本や注釈書がまとめられました。
|

 |
 |
『神農本草経』の特徴は、1年の日数と同じ365種類の植物・動物・鉱物が薬として集録されていること、人体に作用する薬効の強さによって、下薬(げやく125種類)・中薬(ちゅうやく120種類)・上薬(じょうやく120種類)(下品・中品・上品ともいう)という具合に薬物が3つに分類されていることです。
平成21年6月1日より施行された改正薬事法で、医薬品は副作用などによる健康被害の生じるリスクに応じて、第一類・第二類・第三類の3つに分けられ、最も注意が必要な第一類医薬品だけは薬剤師がいる店舗でしか購入できないという規則になりました。すでにこれとよく似た分類が、約2000年前の薬物書で使用の際の危険度に応じて薬物が分類されていたということに驚かされます。
記事:内藤記念くすり博物館
野尻 佳与子 (2009年6月) |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |

