
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
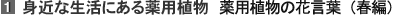 |
 |
 |
 |
3月の初旬、息子が通う保育園に冬眠から目覚めた蛙が姿をあらわし、子どもたちは大騒ぎだったそうです。散歩の際には、小さな花や木々の先に若芽を見つけては「小さな春だね」とささやいています。
春になって大地があたたまり、虫が冬眠を終わらせ地面から這い出てくることを、啓蟄(けいちつ)といいます。古代中国では季節を知る目安として太陽暦をもとにした二十四節気というものがあり、啓蟄はこの季節のひとつです。天文学的には太陽が、天球上のある地点を通過する瞬間を指し、2008年は3月5日だそうです。
さて、今回は春の薬草の花言葉を送らせていただきます。お楽しみいただければ幸いです。
スミレ (花言葉)誠実、ひかえめ
日本では、観賞用に数百種類が栽培されているというスミレですが、実は立派な薬草です。花時期の全草を採取、陰干しをして煎じ液にするか、生の全草を塩で揉んだものを腫れ物の解毒などに用います。
ギリシア神話では、牝牛に変えられてしまった巫女のイオの食事のためにゼウスが生み出したのがスミレだそうです。
微妙な縦模様のはいった小さな花びらを持つスミレの雰囲気とあった花言葉ですね。
レンギョウ (花言葉)かなえられた希望
モクセイ科の中国原産の落葉低木です。早春に葉に先がけて黄色の花を枝一派に咲かせます。この様子から、この花言葉が生まれたようです。
生薬として古くから日本にも伝わっており、漢方で消炎・利尿・解毒などに用いられます。
ハコベ (花言葉)ランデブー
ハンロウ(繁縷)という生薬名を持つハコベは、春の七草のひとつです。昔は葉に塩を加えて歯磨きとして利用していました。利尿作用もあるとして民間で使用されていたそうです。
ハコベは小鳥のえさとしてもよく使われますが、花言葉のランデブーも、ひよこが集まるころからきたそうです。
ジンチョウゲ (花言葉)栄光、不滅
ジンチョウゲの名前は、沈香(ジンコウ)のような香を持ち、丁香(チョウジ)のような花をつけることからこの名がついたとされています。中国が原産の低木で、もともとは歯・のど・腫れ物などの痛みに用いる民間薬として日本に輸入されましたが、香りがよいことから観賞用として広がりました。
遠くまでその香が届いたことから、「栄光」というこの花言葉がつけられたようです。
一方、不滅に関しては由来を調べてみましたがわかりませんでした。挿し木でも簡単に増やせるところからつけられたのでしょうか。
※過日掲載しておりました「ワスレグサ」について、間違った内容が掲載されておりました。深くお詫び申し上げます。
参考文献:花言葉花贈り(池田書店)
記事:エーザイ株式会社
コーポレートコミュニケーション部
谷田部 裕美子 (2008年3月)
|
 |
 |
 |
 |
 |
|

