 |
 |
 |
 |
 |
 |
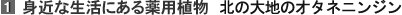 |
 |
 |
 |
江戸時代、八代将軍・吉宗の時代には、生薬を輸入に頼らず国産化する政策が取られていた。中でも江戸幕府が熱心に取り組んだのは、オタネニンジンの国産化である。オタネニンジンはウコギ科の多年草で、朝鮮人参、薬用人参ともいい、漢方では単に人参とも呼ぶ。食欲不振や消化不良、病弱の際の強壮に用いられる生薬である。
『日本薬園史の研究』(上田三平著)には、享保年間(1716-1735)は会津藩や南部藩などで栽培が試みられたと書かれている。『蝦夷地の医療』(札幌医史学研究会編)によれば、幕府は対馬藩や清国の商人から人参の苗や種子を取り寄せては栽培を試み、ようやく種子が自給できるようになったのは、享保10年(1725)のことである。この時に栽培を担当したのが、阿部友之進である。
阿部友之進はもともと医師であったが、海難事故に遭い、たどりついた先の中国で18年にわたって本草学を修め、帰国した人物である。彼は、享保12年(1727)に幕府の採薬使となり、蝦夷(えぞ;現在の北海道)へと派遣された。
採薬使は有用な植物等の探索や実態調査を行うのが目的である。この時は野生人参の捜索が目的であったが、発見はできなかった。しかしながらこの調査で蝦夷が人参栽培に適した土地であることが判明したため、享保20年(1735)に幕府から届いた苗を植えつけたが、成功には至らなかった。 |
|
 |
阿部友之進の死後、宝暦8年(1758)にまとめられた『採薬使記』の奥州之部には、蝦夷に産出する生薬として、タケリ(生薬・海狗腎;オットセイの陰茎)、木耳(菌類の一種・エブリコ)、イケマ(ガガイモ科のつる植物)、独活(ドッカツ;ウド)が挙げられている。当時の蝦夷ではアイヌ民族がさまざまな植物を薬用に利用しており、かの地で採取できる薬草として、附子(ブシ;トリカブト)、竹節人参(チクセツニンジン)、黄連(オウレン)、細辛(サイシン)、縮砂(シュクシャ)、川 (センキュウ)、防風(ボウフウ)などが知られていた。しかし、江差に滞在していた儒者・立松東蒙が天明3年(1783)に著した『東遊記』には、本州から移り住んだ人々の目的は、鰊(ニシン)や昆布、材木などであり、薬用として注目されたのは熊胆(ユウタン;クマの胆嚢)や海狗腎など少数にすぎないと記されている。 (センキュウ)、防風(ボウフウ)などが知られていた。しかし、江差に滞在していた儒者・立松東蒙が天明3年(1783)に著した『東遊記』には、本州から移り住んだ人々の目的は、鰊(ニシン)や昆布、材木などであり、薬用として注目されたのは熊胆(ユウタン;クマの胆嚢)や海狗腎など少数にすぎないと記されている。
蝦夷で人参が再び注目されたのは幕末のことである。幕臣で医師であった栗本鋤雲(じょうん)が薬園を開き、先に人参栽培に成功していた会津藩から栽培に詳しい人材を迎え、種子も提供してもらって栽培が行われた。栽培が軌道に乗り始めた頃は明治維新の動乱期であったため、一時薬園は廃止となったが、その後明治政府下で復活した。現在では北海道は人参をはじめ、当帰、大黄など北方系の薬草の有数の産地となっている。
記事:内藤記念くすり博物館
稲垣 裕美 (2012年9月) |
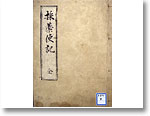
 |
| 『採薬使記』安部照任 松井重康(玄蕃)口述 高木大醇録 (写本) |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| オタネニンジン |
 |
 |
| <参考文献> |
| 北海道の医療史 |
北海道医療新聞社 1976 106p |
| 北海道の医療その歩み |
北海道医史学研究会 1996 344p |
| 北海道の薬草 家庭での育て方,用い方 |
三橋博 山岸喬著 北海タイムス社 1977 232p |
| 北海道の薬用植物 |
本間尚次郎ほか著 北海道衛生部薬務課 1972 83p |
| 北海道の薬用植物 栽培法,収穫時期,調製法 |
本間尚次郎ほか著 北海道衛生部薬務課 1980 78p |
| 北海道薬用植物図彙 (覆刻版) |
工藤祐舜 須崎忠助著 北海道大学図書刊行会 1988 100図 |
| 日本薬園史の研究 |
上田三平著 丸善 1930 247p |
| 人参史 第1-7巻 |
今村鞆著 朝鮮総督府専売局 1934-1940 6冊 [第6巻欠] |
| 蝦夷地の医療 |
札幌医史学研究会編 北海道出版企画センター(制作) 1988 199p |
| 北方の生薬 第1輯 |
北方生薬研究所著 北方出版社 1945 48p |
| 採薬使記 巻之上中下 |
安部照任 松井重康(玄蕃)口述 高木大醇録 写 35丁 |
| 名誉新誌 第11-19号 |
東京 大来社 1876(明治9) 1冊 和 |
|
|
 |
|
 |
 |
 |
 |

