 |
 |
 |
 |
 |
 |
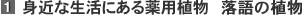 |
 |
 |
 |
代表的な庶民の娯楽であった落語は、室町時代に大名の話し相手をつとめた御伽衆(おとぎしゅう)の話が原点と言われており、大変長い歴史を持つ芸能です。初めての寄席が神田で産声をあげた1798年(寛政10年)から数えても200年の歴史を持ち、舞台装置もなく、座ったままで一人何役も演じる芸は、世界でも類のないものと言えます。
|
 |
噺家は、今も昔と変わらず、カゼ(扇子)とマンダラ(手拭)だけで、あらゆる世界を観客の頭の中に再現します。昨今の映画界等ではSFX(特殊効果)やCG(コンピュータグラフィックス)がもてはやされていますが、人が頭で生み出すイメージの世界は、それらをはるかに越える現実感を私たちに与えてくれます。「何も無いことは、すべてあること」を先人達は良く知っており、舞台装置などはイメージを縛ってしまうものと考え、あえて使わなかったのではないでしょうか。たった17文字で世界を再現する俳句に象徴されるように、日本人は頭の中に仮想現実を創り上げる名人であったといえるかも知れません。しかし、残念なことに、映像が溢れる現代日本では、直接的な視覚に頼りすぎ、これまで培い磨き上げてきた貴重な能力も過去のものになりつつあります。
落語には、季節に逆らわず、その移ろいを楽しみながら生きる庶民の姿が描かれています。ここでは、主役として、時に季節感を演出する名脇役として登場する様々な植物の一部を紹介いたします。私たちが忘れがちな季節感に触れ、失いつつあるイメージ力を取り戻すことができる落語。今こそ見直したい伝統芸能です。
記事:エーザイ株式会社お客様ホットライン室
尾形 武彦(2002年11月) |
![[内藤記念くすり博物館]収蔵資料「美声散」](../../../images/museum/herb/familiar/imageco01.jpg) |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 |
 |
 |
 |

